防災訓練を実施するなら、具体的にどのような内容にすればいいのでしょうか。特に自然災害が激甚化し、企業としても被災リスクが高まっている昨今、いざという時に役立つ訓練を実施したいものです。そこで今回は防災訓練はなぜ必要なのか、防災訓練の種類や進め方について網羅的にご紹介します。
実際に防災訓練を行う上でどういったことに気をつければいいのか、具体的な手順やポイントについてもご説明しますので、ぜひ自社の防災訓練にとりいれてみてください。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
なぜ防災訓練は必要なのか
近年、未曾有の大災害が数多く発生しており、誰もが被災者になる可能性があります。そのため企業も従業員の身の安全を守り事業存続を図るために、事前の防災対策が欠かせません。
防災計画やBCP(事業継続計画)、備蓄品の準備、耐震対策といった事前の備えをしていても、計画を立てただけでは防災にはなりません。従業員自身が自分の役割を知り、いざという時にスムーズに行動できるようにしなければ、会社への被害も大きくなってしまうおそれがあります。だからこそ防災訓練を定期的に行うことで、社員の防災意識の啓蒙や、防災対策の理解を進める必要があるのです。
防災訓練とは

防災訓練にはさまざまな種類があります。災害時に迅速に最適な行動をとり被害を最小限に食い止められるよう、防災知識を身に付け、設備や備蓄を活用する訓練を行います。
ここでは防災訓練の種類や、訓練する必要性についてご紹介します。
防災訓練の種類
連絡・通報訓練
災害発生時の安否確認をスムーズに行うための訓練です。安否確認システムや、緊急連絡網など、BCPで定めた方法に沿って行います。負傷者が出た場合や火災発生時は一刻も早く救急や消防に通報をする必要があるので、通報するべき内容を学んだり、通報時に必要な情報が何かを知ることで、躊躇なく通報できるようになるでしょう。
初期消火訓練
建物に備え付けられている消火設備の確認や使用方法の確認を行う訓練です。実際に建物で火災が発生すると、天井に燃え移るまでには3分程度かかると言われています。天井に燃え移った段階だと、消火器での消火は難しくなるため火災の拡大は免れません。
火災の通報から消防隊が到着するまでは、平均して7~8分程度。自社の従業員だけでも初期消火ができるように日頃から訓練しておきましょう。また、通報訓練も同時に行うといいでしょう。
避難訓練
災害直後、迅速に安全な場所まで避難するための訓練です。地震ならまずは机の下に隠れる、津波や浸水時は高いところへ移動する、火災時は避難経路から外へ出る、という具合に、災害の種類によって行動が変わるので、事前にBCPで避難行動について定めておく必要があります。
また、避難時の誘導や点呼・報告の役割と手順も決めておき、訓練するといいでしょう。エレベーターを使わない避難方法や、火災時の防火扉を閉めるタイミングの確認、担架やAEDなどの設置場所も確認し、活用できるよう計画を立てましょう。
応急救命訓練
心肺蘇生法やAEDの使い方、怪我人の搬送方法、三角巾の使い方など、応急救命の方法を学ぶ訓練です。一人ひとりが対応方法を把握することが、多くの方の命を守ることにつながります。
応急救命の講習は消防署でも開催しているため、ぜひお近くの消防署に問い合わせてみてください。
救助訓練
閉じ込めや備品転倒により人が下敷きになった状態などを想定し、救助用品や身近な道具、工具、担架などを利用して負傷者を救出する訓練です。てこの原理を使った負傷者の救出、ブルーシートや毛布などを担架代わりにした負傷者の搬送方法などを知っておけば、自社の社員はもちろん、周辺住民や来客の命を守ることにもつながります。特に事業所にある道具は家庭用とは違って使い慣れないものも多いので、訓練しておくことがおすすめです。
図上訓練
災害発生を想定して、図上で被害想定や状況整理、対応方法などを学びます。周辺地図やハザードマップを見ながら、防災設備や避難経路の確認、災害リスクの確認などに重きを置いた図上訓練が基本です。防災計画の災害想定シナリオに沿って、災害発生後の手順や対応方法の確認に重きを置いた応用的な図上訓練もあります。
防災訓練の進め方

ここからは、実際に防災訓練をする問題点や手順を解説します。いざというときに訓練内容が役に立たなかったらもったいないもの。参考にして、ぜひ有意義な防災訓練を行ってください。
防災訓練を行う上での問題点
防災訓練を行う企業は多いものの、あらかじめ決まった動きをなぞるだけで、形骸化してしまう事態に陥りがちです。毎度同じ内容や、シナリオがきっちりと決まった訓練では、身が入らないかもしれません。シナリオがない訓練や、いろいろな災害や想定外のトラブルを織り込み、訓練参加者が主体的に考えて取り組めるよう工夫しましょう。
また、その土地柄に合った訓練をしっかり行うことも重要です。海、山、川、森林など近くにあるものでどんな災害が起こりやすいかは変わってきます。ハザードマップを定期的に確認し、災害リスクに応じた訓練を行いましょう。
防災訓練のポイント

Place wooden blocks on the pyramid. 100 percent work safety concept.
防災訓練を形骸化させないためには、参加者に「当事者意識を持たせること」が必須です。そのためには以下に挙げるポイントを抑えながら訓練を行ってください。
目標の明確化
防災訓練を通して参加者に「何を学んでもらいたいのか」「何を考えさせたいのか」。この目標によって訓練の形式は大きく変わります。
防災計画やBCPで策定している対策や手順の確認が目標であれば、事前に参加者には対策を理解してもらいます。BCPに沿った行動を実際に起こすためには各自が責任感をもって行動する必要があり、実際に訓練してみれば、備品や防災知識の不足といった課題が見えてくるもの。目標を的確に設定し、各自が行動を起こせる状態を目指しましょう。
災害状況の設定
地震や風水害などの場合は、自社の所在地から想定される最大規模の災害を設定します。よりリアリティを高めるためには、過去の災害事例や被災経験を参考にするのもいいでしょう。
災害状況を設定する際は、少なくとも下記の項目が必要です。
- 災害発生日時、場所
- 災害発生規模
- 被害想定(自社施設内の状況、被災者状況、二次災害の発生有無)
- ライフラインや公共交通機関への影響
計画書の策定
目標とおおよそのシナリオが決まったら、計画書を策定しましょう。計画書は参加者に対して事前に公表し、なぜ訓練を行っているのかがわかるようにします。実際に計画書を作るときには下記の項目を設定してください。
- 訓練の目標
- 訓練日時の設定
- 会場の設定
- 参加者の範囲
- 災害のシナリオ
- 訓練内容
- 必要な資機材
- 実施スケジュール
- 訓練を通じて得られる成果
振り返り
次回の防災訓練に反映させるためにも、振り返りは必ず行います。参加者のアンケートはもちろんですが、事前に立てた目標と照らし合わせて達成度を測ることも重要です。設備の不具合や役割分担が不明確なところは迅速に改善しましょう。
防災訓練の手順

Top view of emergency backpack preparations with necessities
今回は、防災訓練の種類でご紹介した図上訓練をもとに手順を解説していきます。図上訓練は低コストで準備の負担も少ない訓練なのでおすすめです。
事前の準備物
企業で実施する場合は社内の見取り図を用意します。また地図に書き込みを行うため、透明シートや油性ペン、付箋、カラーシールを用意しましょう。
地図の作成
図上訓練はグループにわかれて行います。見取り図をもとにどんな防災設備があるのかを確認し、見取り図に書き込みます。またグループ内で社内の状況を思い出しながら、各所にどんなリスクがあるかを話し合いましょう。
避難経路上に邪魔になる荷物はないか、災害時に転倒や移動する什器はないか、火災の危険性が有る場所はないかなどを確認してください。
被害想定の記載
ある程度書き込みが終ったら、透明なシートをかぶせて、災害発生時にどんな被害が想定されるかを書き込んでいきます。
想定訓練
書き込みを行った地図と、事前の災害発生シナリオをもとに、どんな対応をとるべきかをグループ内で話し合います。司会者が災害状況を説明し、その都度グループ内で、災害発生時にとるべき対応を話し合いましょう。訓練を通して自社の防災対策の見直しや、災害時にとるべき行動を知り、防災意識を高めることができます。
イベントとして行う防災訓練も
防災運動会

運動会に防災知識を取り入れ、運動会として楽しみながら防災に関する知識や知恵を身につけられるアクティビティ。防災を「事前準備/災害発生/発生直後/避難生活/生活再建」の5つのフェーズに分け、自分で助かる・他人を助けることの大切さを学べます。年齢や性別問わず楽しく学べるので、企業運動会やレクリエーションとして、防災意識を高める啓発イベントとしても利用されています。
防災運動会の資料ダウンロードはこちら
防災謎解き

防災謎解きは、災害時をテーマにした謎解きゲーム。謎解きを楽しみながら、災害発生時に取るべき行動・判断や、災害時に非難すべき場所、自分が助かる「自助」、周りと協力し合う「共助」の考えなどを学べます。
また、謎を解く過程でチームでの役割分担や協力が促されるため、防災訓練として取り入れるだけでなく、チームビルディングを目的とした社内イベントとしても人気があります。
防災謎解きの資料をダウンロードする防災コンセンサスゲーム
防災コンセンサスゲームは、防災士監修のストーリーのもと、災害発生時の対応を考え、学べるゲームです。災害によって帰宅困難になった場合の対応を個人で考え、チームで議論する過程で、合意形成(意見の一致)を体験でき、防災に関する考え方や知識の共有が可能です。
また、チームで最適解を出すためには人の話を聞き、協調性を持つことが重要で、このゲームを通してコミュニケーションの必要性を理解でき、コミュニケーションが促進されます。
防災コンセンサスゲーム「帰宅困難サバイバル」の資料をダウンロードする東京消防庁公式YouTubeチャンネル
東京消防庁の公式YouTubeチャンネルでは、コロナ禍でも防災訓練ができるようにリモート防災訓練という動画を公開しています。消火器の使い方や、火災時の避難の方法、119番通報の方法などが公開されてり、基本的な防災知識を学ぶのに最適です。
オフラインの訓練で学ぶことが難しい状況では、このような動画コンテンツを積極的に使い、防災知識を高めることもおすすめです。
まとめ

企業が被災すると、従業員の安全だけでなく事業中断のリスクもあり、社会にいろいろな影響を及ぼすこともあります。緊急時にも迅速に行動し、被害が最小限に食い止められるよう、日頃から訓練を行うことが大切です。そして、ただ漫然と訓練を行うのではなく、参加者に当事者意識をもたせる訓練内容にすることが必要でしょう。
自社で作成した防災計画やBCPが計画をいざという時に生かせるよう、今回紹介したような防災訓練に取り組み、定期的に社内の防災意識を高める体制を整えてみてはいかがでしょうか。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
防災に役立つ豆知識が得られる記事はこちら!
防災の豆知識!知っておくと役立つ20の知識

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!

「やらないと」から「やってみたい」と思える防災へ。防災を楽しく学べるイベント「あそび防災プロジェクト」の発案者。防災運動会をはじめとした様々なサービスを考案。企業や自治体、商業施設での防災イベントの実施や、「世界防災フォーラム2019」「防災アイディアソン BOSAI Startups in Japan」へ登壇。「あそび防災プロジェクト」は2020年グッドデザイン賞を獲得した。



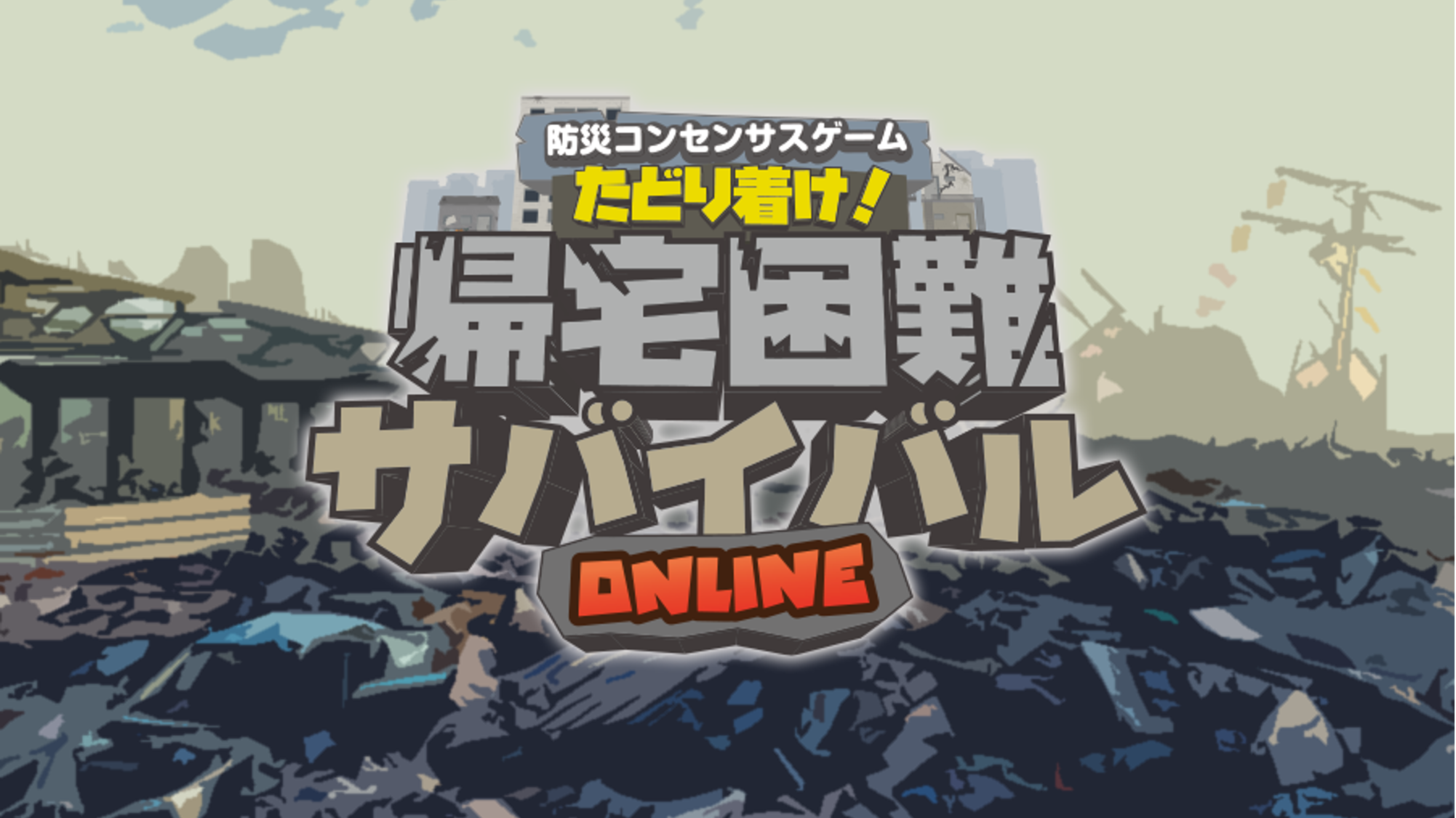

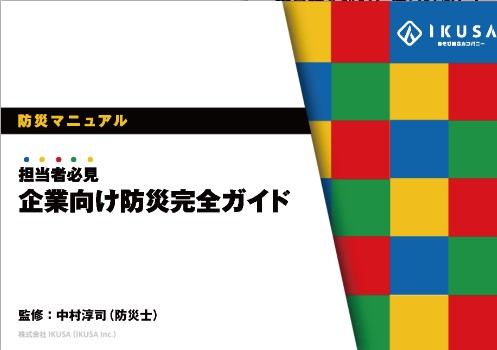





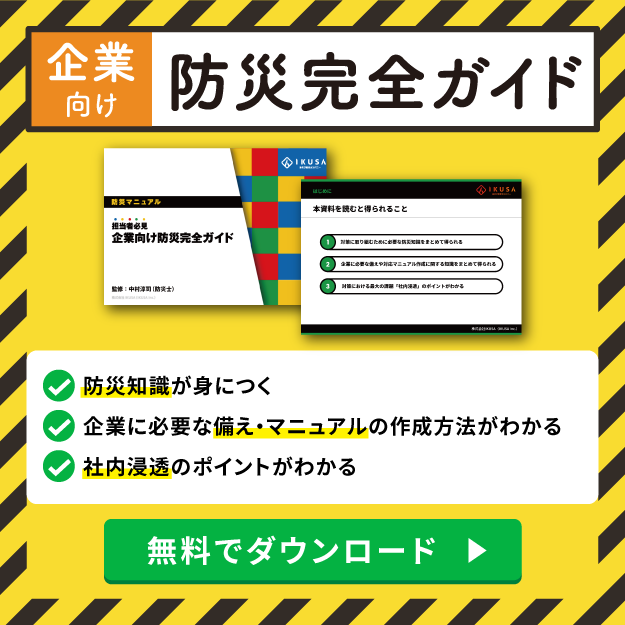







 kana
kana
 JJ
JJ




