災害大国である日本において「防災」対策は欠かせません。しかし一方で、近年は「減災」の必要性が叫ばれています。防災も減災も同じような意味で扱われることがありますが実際は明確な違いがあり、近年の自然災害に対応するためには「減災」の考え方が重要になります。
本記事では、減災の概要や、防災との違い、防災や減災の課題を解説します。現代の日本で「減災」が重要な理由に迫っていきましょう。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
減災とは?

まずは、減災とはどのようなものなのかを解説します。概要を理解して、減災の基本を知っておきましょう。
災害による被害を最小限に抑えること
減災とは、災害による被害を最小限に抑えることをいいます。地球温暖化の影響から頻発化している近年の豪雨災害や巨大台風、またいずれ来るといわれる巨大地震についても、すべての被害を防ぐことは不可能といえるでしょう。そのため、災害が起こることを前提とし、いかに被害を抑えるかが非常に重要とされています。
企業であれば、従業員の命を守るための取り組みはもちろんのこと、BCP(事業継続計画)を立て災害時の損害を抑えることも、減災の取り組みの一つといえるでしょう。
災害が発生することを前提に対策する
減災は、災害が発生することを前提として対策することでもあります。
もともと日本は古くから災害に悩まされてきた国ですが、現代は地球温暖化の影響などにより、異常気象や過去に記録したことがないほどの被害をもたらす自然災害が相次いでいいます。このことから、自然災害を食い止めることは不可能として、国土交通省が「減災」を提唱しました。これが、一般的に認識されている「減災」の始まりです。実際、「南海トラフ巨大地震」「首都直下型地震」「噴火」など、懸念されている自然災害は多く、発生する確率も極めて高いといわれています。
こうした状況をふまえると、「災害を防ぐ」という取り組みは難しく、「災害が起きた後の被害をいかに抑えるか」が大切であると分かります。
減災と防災の違い

減災と似たワードとして「防災」が挙げられますが、それぞれ具体的な違いについて正しく把握している方は少ないものです。ここからは、減災と防災の違いについて解説します。
災害の発生が前提であるか否か
減災と防災の大きな違いといえるのが「災害の発生が前提であるか否か」です。
減災は、前項でも触れたとおり「災害が発生すること」を前提としているのに対し、防災は災害の発生が前提ではありません。今の地形や気象情報から考えて、どんな災害が起こるのかを具体的に考え、起こった際の避難行動や事業継続の計画を立てることが減災ということになります。
災害を食い止めることが防災
防災は災害を食い止めることを目的としているのが特徴です。例えば、津波や河川の氾濫を防ぐためにも防波堤を作ったり、万が一災害が発生しても被害を0にするために準備するということです。
しかし、2011年の東日本大震災では津波が防波堤を越えてきたり、思ってもみないところで土砂災害が起こるなど、想定外の災害が起こるリスクは非常に高まっており、すべてを予防することは不可能でしょう。一方で減災は、災害が発生することと、ある程度の被害があることを前提としているため、大きな災害のリスクを抱えている日本において適した取り組みといえます。
減災・防災の課題について

減災も防災も「災害対策」という意味では重要です。しかし、現在の日本ではこの減災・防災でさまざまな課題が挙がっている状況でもあります。
ここからは、減災・防災の課題について解説しますので、自社や家庭の状況と照らし合わせながら、問題点を探してみてください。
高齢家族の避難
減災・防災の課題として、まず挙げられるのが「高齢家族の避難」です。
現在、日本は高齢社会の真っただ中であり、高齢者がいる家庭や、高齢者の単身世帯が多くなっています。高齢者は体が不自由であったり、寝たきりであったり、災害発生時にスムーズに避難する、というのが困難な場合があります。
大きな災害が起きることを想定し、家族で対処法を話し合っておくことが重要です。
ペットとの避難
また、課題のひとつに「ペットとの避難」があります。災害が発生した場合、自宅での待機が難しいときには避難所の利用が必須です。しかし、避難所の多くが「ペット同伴禁止」となっています。
これは、他の利用者に配慮したものであることが多く、ペットと一緒に暮らす家庭においては大きな問題であるのが現状です。ペット同伴ができる避難所もありますが、全体で見るとかなり少数派であり、また仮にペット同伴が可能な避難所であっても、他の利用者とのトラブルを懸念して、利用を控えるといったケースも少なくありません。
ペットと暮らす家庭では、近くの避難所がペット許可しているか事前に確認しておくことが大切です。
避難しないという選択
減災や防災の課題のひとつに、「避難しない」という選択肢があることが、周知されていないという点があります。大きな災害があると、「避難所へ行く」という選択肢が挙がりがちですが、必ずしも避難所に行くことが減災・防災につながるとは限りません。
例えば、大雨によって河川の氾濫や洪水が懸念される場合、タイミングによっては既に道が冠水するなど危険な状態になり、避難するという行動が二次災害を引き起こす場合があります。正しい状況を迅速に受け取り、その時に適した判断をすることが求められます。
地域とのつながり
現代の日本ならではの課題ともいえるのが「地域とのつながりの希薄さ」です。
かつては、災害が発生すれば近隣住民などと協力しながら、被災生活を乗り越えてきたといった歴史があります。しかし、現代の日本は基本的に地域とのコミュニケーションが少ない傾向であるのが現状です。
実際、隣近所に住む入居者の顔や名前を知らない、といったケースは多く、災害が発生した場合の地域住民での協力が見込めないことも考えられるのです。いざというときに助け合えるよう、日頃から地域の防災訓練などを行い、交流を持つようにしましょう。
日頃からの備え
減災・防災の課題として、最も大きなものであるのが「日頃からの備えが不足している」という点です。災害による被害を最小限に抑えるためには、日頃から災害の発生を想定して、物資などを揃えておく必要があります。
日頃忙しく過ごしている企業や家庭では、いつかは備蓄品を揃えようと考えながらも、なかなか実現していない場合もあります。また、備蓄だけでなく室内の家具の固定や耐震ガラスなど、災害発生時を想定して生活環境を整えることも大切です。9月1日の防災の日などをきっかけとして、企業・家庭の減災対策は見直しておくとよいでしょう。
減災・防災意識の向上におすすめのアクティビティ3選
減災・防災に関する意識を高めて自分ゴト化させるには、体験型のアクティビティを活用することが効果的です。防災意識の向上に役立つアクティビティを3つご紹介します。
防災運動会
防災運動会は、運動会に防災知識が得られる要素を取り入れ、体験を通じて防災について楽しく学べるアクティビティです。防災を事前準備・災害発生・発生直後・避難生活・生活再建の5つのフェーズに分け、オリジナルの運動会種目をおこないながら、参加者が防災知識を学べます。地域や参加者に応じて競技をカスタマイズすることもできます。
防災運動会の資料ダウンロードはこちらおうち防災運動会
おうち防災運動会は、防災をテーマにしたオンライン運動会のアクティビティです。防災に関心がない子どもも楽しく学べる仕掛けがあることが特徴で、家にいるからこそできる競技を通じて、家族と一緒に防災について考えることができます。
おうち防災運動会の資料ダウンロードはこちら防災謎解き

防災謎解きは、防災テーマの謎解き脱出ゲームをおこなうアクティビティです。チームで協力して謎を解き、脱出することを目指します。リモート開催のオンライン防災謎解きもあり、リアル・オンラインの両方で実施可能です。
防災謎解きでは、謎解き体験を通じて防災知識を得られるため、深く理解し、学びを定着させることができます。また、ゲームには謎解き以外の要素も含まれており、謎解きが苦手な方も楽しめることも特徴です。
防災謎解きの資料をダウンロードする防災コンセンサスゲーム
防災コンセンサスゲームは、帰宅困難時の考え方や災害発生時の対応について学べるアクティビティです。防災士監修の元で開発され、災害時の適切な対処や行動を、コンセンサス(意見の一致)を図るプロセスを通じて深く理解することができます。
防災コンセンサスゲームでは、まずは個人ワークで対処法の優先順位を考え、次にグループワークをおこなってチームとしての答えを出します。意見を出し合い、互いに尊重し合うことでコンセンサスを得られます。
防災について深く考える機会になることはもちろんのこと、チーム内で価値観や考え方を共有し、参加者がコミュニケーションの必要性を理解できることが特徴です。
まとめ

本記事では、減災・防災について解説しました。
災害に対する備えをする際には、防災と減災の両方について考え、対策を講じることが重要です。災害発生を前提に対策をしておくことは、被害を最小限に抑えたり、災害後の復旧を迅速にしたり、負担軽減することにつながります。
日本は地震や水害の多い国であり、常に災害リスクが身近にあります。減災・防災を自分ゴトとして捉え、防災対策や防災訓練などに取り組みましょう。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
減災・防災に役立つ豆知識が得られる記事はこちら!
防災の豆知識!知っておくと役立つ20の知識

株式会社IKUSAのオウンドメディア担当。「あそび防災プロジェクト」をはじめとするメディアの編集長を務めています。記事の編集、校正、アナリティクス分析、駆け出し動画編集、WEBデザイン、メルマガ企画など遊びの会社の1人マーケターとして奔走中!





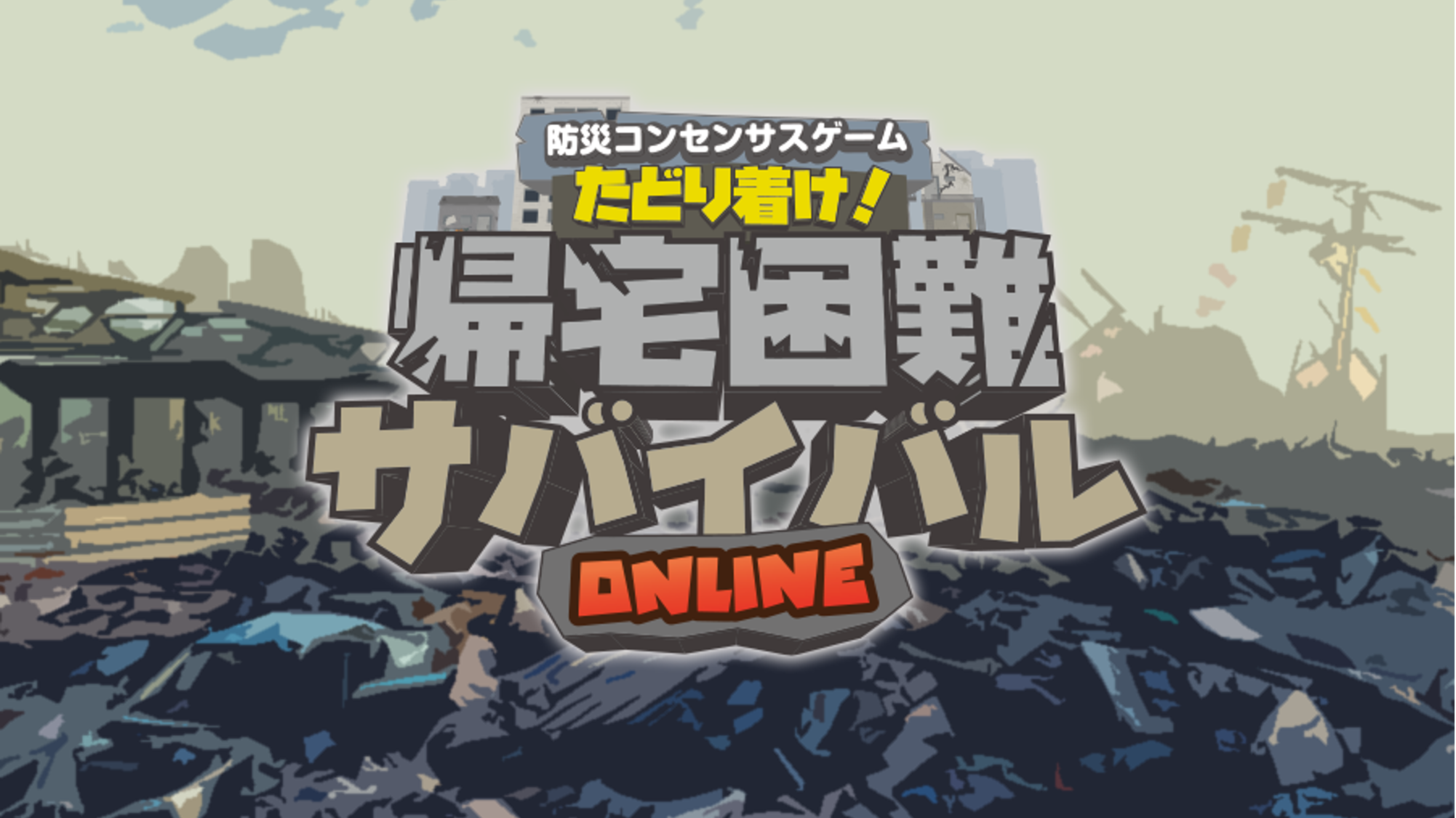

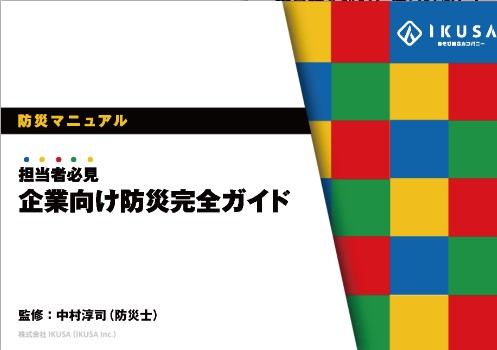





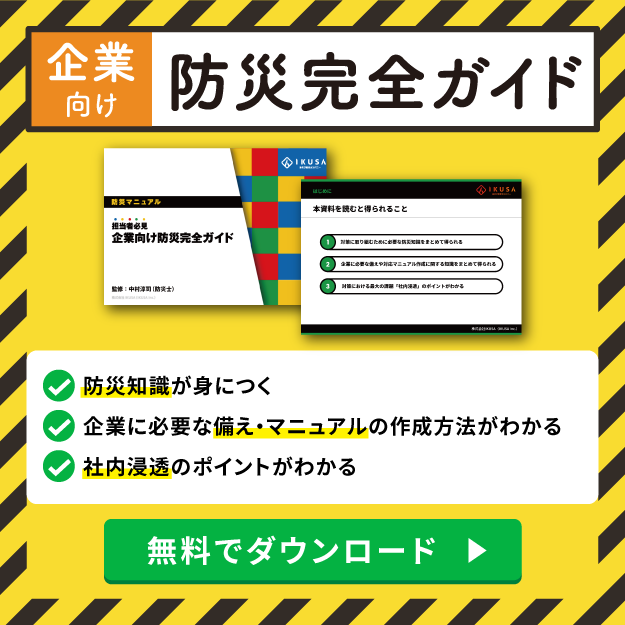


 あそび防災情報局
あそび防災情報局
 粕谷麻衣
粕谷麻衣



 萩 ゆう
萩 ゆう




