防災士とは、「自助・共助・協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した資格です。年齢・性別・学歴等の制限はなく、誰でも取得することができます。
将来起こるとされている「首都直下地震」「南海トラフ巨大地震」をはじめ、水害や台風などさまざまな災害が身近になった今、企業や自治体にも防災対策が求められており、企業の防災担当者や市区町村の職員にも資格取得が推進されています。
本記事では、防災士資格の概要や防災士に求められる役割、防災士資格取得のメリット、防災士資格取得の費用や、費用を安く抑える方法、防災意識を高めるおすすめのアクティビティについて解説します。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
防災士とは

防災士とは、社会のさまざまな場で防災力を高める活動が期待され、防災に対する一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構から認証されることで取得できる資格です。
1995年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害時に正しい知識と適切な判断力を兼ね備えた人材を育てることを目的として、2003年から制度が運用されました。学校、福祉施設、企業などで防災士の配置や活用の動きが広がっています。
防災士は国家資格ではないものの、防災関連の民間資格の中ではメジャーな資格であり、現在(2023年8月)までに26万名以上が日本防災士機構によって認証されています。万が一の災害に備えて少しでも防災の知識を深めたい、災害時に役に立ちたいなどの理由から、防災士を取得者は年々増加傾向にあります。
また、日本防災士機構が認証した全国の地方自治体や国立大学などの教育機関、民間研修機関などでも防災士の養成事業を行っています。
防災士に求められる役割

防災士は民間資格であるため、資格取得により特定の権利を得る、義務的な行動が求められるなどはありません。しかし防災士は、「自助・共助・協働を原則として、様々な場で防災力を高める活動が期待されている資格」であることからも、災害時・平常時それぞれにおける防災関連の重要な役割が求められています。
平常時の活動
まずは自身や家族を守るために家具の固定、非常食の備蓄など備えを進めます。そのうえで、地域や職場での啓発活動や訓練の実施、さらには地域の自主防災組織や消防団の活動への参加などを通じて、周囲の人への防災啓発活動も期待されます。リーダーとして率先して動き、周囲の人を動かすよう努めていきます。
災害時の活動
被災した際は、災害時に自身を守ることはもちろんのこと、避難誘導や初期消火、救出救助活動などに当たります。東日本大震災や熊本地震においては、防災士のリーダシップによって住民の命が救われたことや、避難所開設がスムーズに運んだという事例が多数報告されています。
自身が被災しなかった場合、災害発生時には被災地支援活動を行います。被災地の復旧・復興に向けたボランティア活動や物資の調達・運搬などの支援活動も担います。
どんな人が防災士資格を目指すのか

自然災害大国の日本で注目される防災士ですが、どのような人が防災士の資格取得を目指すのでしょうか。
多くは、企業の防災担当者や危機管理担当者など、組織内で防災の知識が求められる職場に所属している方が防災士資格の取得を目指す傾向にあります。企業が被災し事業中断に陥るリスクが身近になっている昨今、企業にとって防災対策は喫緊の課題であるため、より高度な防災知識をもつ人材が求められています。
一方、学生や主婦の方や地域の町内会や消防団に所属している方などが、地域防災や自己研鑽のために防災士資格の取得を目指すことも少なくありません。中には全職員が防災士資格取得を目指す自治体もあり、老若男女問わず、防災士資格の需要はますます高まっています。
防災士を取得するメリット

実際に防災士の資格を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
防災の知識を活かした活動ができる
防災士の知識や知見を活かせることが防災士を取得する大きなメリットです。防災士は民間資格であるため、取得したからといって特別な権利を得たり、義務的な行動が発生したりすることがなく、基本的にはボランティアです。しかし、災害時に周囲の人が慌てる状況でも家族や周囲の人に避難を呼びかける行動ができたり、避難生活にもしっかりと対応できるなど、身近な人の支えになれるでしょう。
また、社内の防災教育や防災啓発活動、地域の防災活動への協力など、防災に関するさまざまな場面で防災知識を活かした活動ができるようになります。
防災士による企業の防災対策
企業には、災害時における従業員の安全確保や迅速な事業復旧などの責任があります。災害時の行動を規定した防災マニュアル、オフィスの安全対策、さらにはBCP(事業継続計画)の立案など、具体的な対策が求められています。
企業の防災担当者が防災士資格を取得することで、その知識を活かした防災対策を実施することができます。非常食や備蓄品の見直し、防災マニュアルの作成・共有、防災マニュアルに沿った防災訓練の実施など、被害を最小限に食い止めるためにも防災士の知識が役立ちます。
防災士資格の取得方法

次は、防災士資格の取得方法について解説します。
防災士資格を取得するためには、日本防災士機構が認証した研修機関が実施する防災士養成研修講座を受講し、研修履修証明の取得を目指します。養成研修講座は21講目のうち最低12講目以上を履修することが求められ、履修しなかった講目は各研修機関が定めた様式のレポートなどの提出が必要です。
養成研修講座では、「近年の自然災害に学ぶ」「防災士の役割」のような基本的な内容から、「被害想定・ハザードマップと避難」「公的機関や企業等の災害対策」など、防災に関する幅広い知識を学びます。養成研修講座を履修後、その会場で防災士資格取得試験が行われます。3択式で30問出題され、80%以上の正答で合格となります。
また、全国の自治体や地域消防署、日本赤十字社などの公的機関やそれに準ずる団体が主催する救急救命講習(心肺蘇生法やAEDを含む3時間以上の内容)を受け、その修了証を取得することも必要になります。
防災士資格取得試験の合格と、救急救命講習が修了した後に、日本防災士機構へ防災士認証登録申請を行い、防災士認証状と防災士証(カード)を交付され、晴れて防災士となることができます。
防災士資格の取得までにかかる費用
資格取得と聞いて気になるのが、取得にかかる費用でしょう。防災士資格取得にかかる費用は、以下のようになっています。
- 防災士研修講座受講料「50,728円(税別)」
- 防災士資格取得試験受験料「3,000円」
- 防災士資格認証登録料「5,000円」
これに消費税を加え、取得までにかかる費用の総額は63,800円となります。
防災士資格費用を安く抑えて取得する方法

防災関連の資格として非常に魅力的な防災士資格ですが、取得までにかかる費用は総額でおよそ64,000円と、決して気軽に受験できる金額ではありません。資格取得を躊躇する人もいるでしょう。
防災士資格取得にはいくつか方法があり、助成金を活用できる場合もあります。次は、防災士資格の費用を安く抑える方法について解説します。
自治体の公布する助成金
防災士資格取得にかかる費用や教本代、講座受験料、防災士認証手続料などについて、一定条件を満たした住民に対して費用の一部または全額を助成している自治体が増えています。
助成内容は自治体によってさまざまですが、費用を少しでも安く抑えたい方や、地域防災に貢献したいという方は一度、お住まいの自治体の公式ホームページや窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、日本防災士機構の公式ホームページにも助成を実施している自治体のリストがあるので、確認するのがおすすめです。

特例措置
防災士資格取得には、現在までに防災や災害対応、応急手当などの実績がある方を対象として、特例制度を設けています。特例措置の対象者は、警察官・消防吏員・消防団員・赤十字救急法救急員資格認定者、自衛隊員の5者であり、これらに該当される方で一定の条件を満たしている場合には、特例措置として防災士試験となどの免除となります。
詳細については、日本防災士機構のホームページをご覧ください。
赤十字救急法救急員資格の取得
特例措置のうち、赤十字救急法救急員の資格は、これまで防災に携わった経験がない人でも取得することができます。
赤十字救急法救急員資格とは、日本赤十字社が認定する民間資格の1つであり、心肺蘇生の国際的な基準に沿った赤十字救急法を実践する知識と技術を有している人に与えられる資格です。
赤十字救急法救急員の資格を取得するためには、救命手当を学ぶ赤十字救急法の基礎講習と、応急手当を学ぶ救急法養成講習の2つの講習を受講し、筆記試験および実技検定試験に合格することが必要になります。
赤十字救急法基礎講習は4時間、赤十字救急法養成講習は10時間ほどで、計3日間の講習です。取得費用は概ね3,000円代と、防災士よりも気軽に受講することができる講座となっています。
この赤十字救急法救急員資格認定者となれば、およそ37,400円で防災士の講座を受けることができます。通常の防災士資格取得費用がおよそ64,000円であるので、かなり費用を軽減することができます。
楽しく防災を学べるアクティビティ4選
防災士の資格を習得したけれど、社内の防災訓練や学校の防災教育にどのような企画を実施するのがよいか悩んだ際には、以下のものを取り入れるのがおすすめです。
防災ヒーロー入団試験
防災ヒーロー入団試験は、頭と体を使って楽しく防災を学べるアクティビティです。災害を事前準備・災害発生・発災直後・避難生活・生活再建という5つのフェーズに分け、それぞれのフェーズに応じた競技を通じて防災を体験できます。
種目は楽しいだけでなく実際に役立つ内容になっており、クリア後には防災メダルが授与されるため、防災教育に最適のアクティビティです。また、集客力が高く、商業施設イベントや地域イベントで人気が高いことも特徴です。
災害都市からの大脱出
災害都市からの大脱出は、防災の知識を学べる周遊型謎解きゲームです。謎解きゲームを楽しみながらも、街の危険区域や避難場所、施設の避難経路を実際に通って知ることができます。
パネルと問題用紙さえあれば、屋内外問わずどこでも実施でき、短期間で用意が可能。施設や地域の防災イベント、ファミリー参加型の社内イベントなど、幅広く活用することができます。
防災運動会
 運動会ならではの競技を通じて楽しく防災を学べるアクティビティです。防災を「事前準備/災害発生/発生直後/避難生活/生活再建」の5つのフェーズに分け、それぞれに応じた競技を行います。地域性や土地柄、参加者の属性に合わせて競技をカスタマイズすることができるので、社内研修や自治体のイベントとしてもおすすめです。
運動会ならではの競技を通じて楽しく防災を学べるアクティビティです。防災を「事前準備/災害発生/発生直後/避難生活/生活再建」の5つのフェーズに分け、それぞれに応じた競技を行います。地域性や土地柄、参加者の属性に合わせて競技をカスタマイズすることができるので、社内研修や自治体のイベントとしてもおすすめです。
防災フェス
防災フェスは、大人も子どもも楽しめるフェス型の防災イベントです。イベントの企画、食事の手配、会場の装飾・演出、集客、写真・動画撮影まで、一貫して年間イベント数1,000件のIKUSAにおまかせできます。
地域や来場者の客層に合わせた「地産地防」のイベントを企画することができるため、商業施設のファミリー向けイベントや、地域・自治体の防災啓発イベントにおすすめです。
資料をダウンロードするまとめ

今回は、防災士の概要や求められる役割、防災士資格の取得方法について解説しました。防災士は民間資格ではあるものの、災害リスクが高まっている昨今、暮らしにもビジネスにも欠かせない、今後も需要が高まる資格です。
また、防災士資格取得には費用がかかるものの、自治体の助成や特例措置を活用することも可能です。防災に興味を持っている方や、今後予想される大災害に備えて少しでも防災の知識を勉強したい方は、ぜひ防災士資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
防災に役立つ豆知識が得られる記事はこちら!
防災の豆知識!知っておくと役立つ20の知識








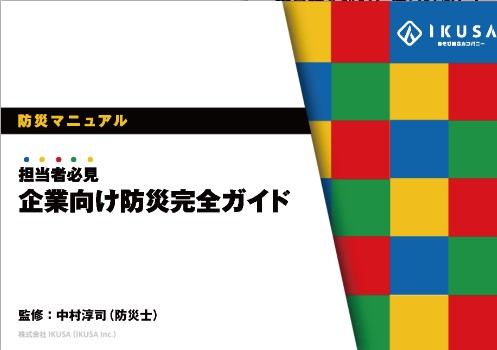





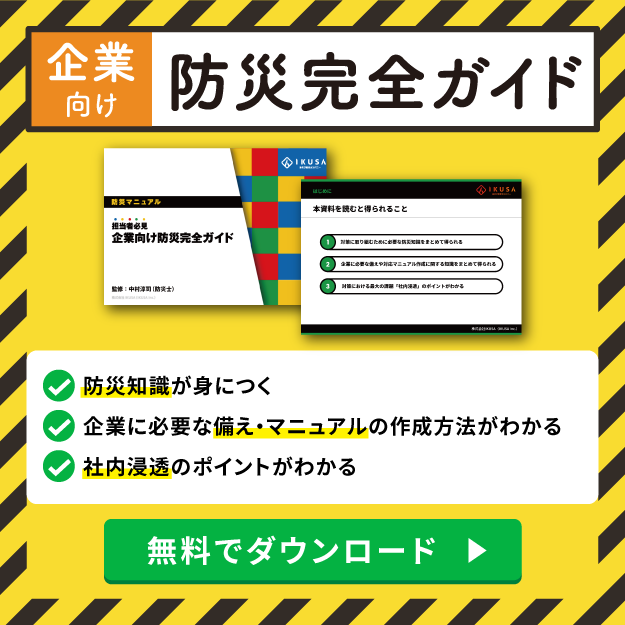



 粕谷麻衣
粕谷麻衣

 粕谷麻衣
粕谷麻衣
 JJ
JJ





