防災グッズと言えば、購入して揃えるのが一般的ですが、簡単に手作りすることができるものも多くあります。自作する方法を知っておくことで、被災時に即席の防災グッズを作成することもできます。
本記事では、10種類の防災グッズの作り方を紹介します。家にあるものだけで作れるものばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
防災グッズを手作りしてみよう!

手作りの防災グッズというと「本当にきちんと使えるの?」「いざというときに活用しても問題ない?」など、さまざまな不安や疑問を持つかもしれません。しかし手作りの防災グッズであっても十分に活用することができます。
手作りに慣れておけば、物資不足でもその場にあるもので作れるようにもなります。また、被災した際に臨機応変に行動する意識にもつながるので、ぜひ防災グッズの手作りにチャレンジしてみてください。
手作りできる防災グッズ10選

どのような防災グッズであれば手作りで準備できるのでしょうか。さっそく作成手順や取り入れ方などを紹介します。
防災スリッパ
「防災スリッパ」は新聞紙があればすぐに作れます。完成したら一度着用して履き心地を試してみましょう。新聞紙ですのでかんたんにサイズ感を調整できます。足元をガラスの破片などの危険物から守るためにも、1人1足ずつの防災スリッパを準備しておくと安心です。
手作り防災スリッパの作り方
- 新聞紙を半分に折る
- 横向きにして上部3分の1くらいを手前に折る
- 裏返して一旦半分に折って折り筋をつける
- 「3」の折り筋に向かって左右の端から折る
- そのまま本を閉じるように半分に折る
- 裏返して完成
防災スリッパが非常時に役立つ!おすすめ商品や手作りする方法を解説
紙食器
紙食器は、物資不足や水不足に陥りやすい災害現場で、気軽に食器を使えるアイデアとして優れています。作り方も、折り紙や新聞紙で作ったお皿やコップに清潔なビニール袋を被せるだけとかんたんです。
紙のまま使用するわけではなく、ビニール袋を被せることで「水に強くなる」、「清潔な食器になる」といったメリットがあります。とくに水分補給のためにコップを使用する場合、紙のままでは時間が経つと柔らかくなったり破けてしまったりすることがあります。紙でコップを作ってから清潔なビニール袋を被せて使えば、手元に食器がなくても水分を補給できます。
また通常の食器とは異なり、皿洗いの手間も生活用水も必要ありませんので、災害時でも気軽に使用できるのがうれしいポイントです。
手作り紙食器の作り方
- 折り紙や新聞紙でお皿やコップの形を作る
- 清潔なビニール袋をかぶせる
- テープなどでビニール袋を止めて固定する
レインコート
レインコートは、雨をしのぐほかにも「粉塵から身を守る」「風を通さないから寒さ対策になる」など、さまざまな効果のある防災グッズです。
レインコートは大きめのポリ袋が一枚あればかんたんに手作りできます。ポリ袋を被るイメージで、「首」「両腕」を通す部分に切り込みを入れるだけ。大きく切りすぎると裂けてしまう可能性がありますので、「切れ込みを入れる程度」にすることがポイントです。
ビニール袋でできているのに意外にも温かさを感じますし、しっかりと水濡れを防いでくれますので、天候の悪いときに活躍してくれるでしょう。
手作りレインコートの作り方
- 大きいポリ袋を被るイメージで頭の腕を通す位置に切れ込みを入れる
- 頭を通す位置に小さめのポリ袋を防水テープで貼り付ける
マスク
物資不足の際に不安なのが「マスク不足」の問題。防災グッズとして準備している分だけでは、使い切ってしまう可能性もありますので、手作りすることも視野に入れましょう。
マスクを手作りする場合はキッチンペーパーを使用します。まず、キッチンペーパーを蛇腹折りにしてください。キッチンペーパーの両端に輪ゴムをあてて、それぞれホチキスで止めます。マスクを広げるようにしてキッチンペーパーを広げ、着用感をチェックしてみましょう。
サイズが合わない場合には、必要に応じて輪ゴムを結んで追加するなど、着用感に合わせて調整してください。
手作りマスクの作り方
- キッチンペーパーを蛇腹折りにする
- 両端に輪ゴムを当ててホチキスで止める
- サイズが合わない場合は輪ゴムを追加して伸ばす
ランタン
災害時は停電が多いので「ランタン」は必需品です。しかし家庭によっては、懐中電灯はあるけれどランタンがないケースがあります。そのようなときには懐中電灯とペットボトルを使った手作りランタンがおすすめです。
まず、ペットボトルの口いっぱいに水を入れてください。しっかりと蓋を閉めて、ペットボトルの底から懐中電灯の光を照らすだけで、即席ランタンの完成。ペットボトルの水が光を反射し、懐中電灯の明かりを拡散してくれるため、全体的に明るさが広がる構造です。
小さなペットボトルでも十分ランタンとして活用できますので、家にあるペットボトルで試してみてください。
手作りランタンの作り方
- ペットボトルに水を入れる
- ペットボトルの底から懐中電灯で照らすようにテープなどで固定する
簡易トイレ
災害が発生したとき、もっとも困りやすいのがトイレですが、外にも家にあるさまざまなもので解消できます。たとえば、段ボールやバケツなどにビニール袋を被せ、その上に小さくちぎった新聞紙をたくさん入れれば簡易トイレになります。
段ボールやバケツがない場合には、新聞紙で箱型に折って活用する方法もあるでしょう。使い終わったらそのままビニール袋の口を縛れますので「ニオイ対策」にもなります。
手作り簡易トイレの作り方
- 段ボールやバケツにビニール袋を被せる
- ビニール袋のなかに小さくちぎった新聞紙などを入れる
おむつ
災害時に不足しやすいおむつはレジ袋で代用できます。ビニール袋を使うので排泄物が漏れる心配が少ないことが特徴です。またタオルをなかに敷くことで、赤ちゃんの肌にレジ袋が直接当たることもなく、肌触りのいい簡易おむつになります。
手作りおむつの作り方
- ビニール袋の両脇を切る
- 「1」を開いて清潔なタオルを上に重ねる
- 「2」を縦向きに置いて上のほうへ赤ちゃんを乗せる
- レジ袋の持ち手を赤ちゃんのお腹へまわして結ぶ
- 下の端を「4」の奥から手前に通す
- 余った部分はお腹側で結ぶ
ペットボトルろ過器
ペットボトルろ過器は、「飲み水不足」で重宝する防災グッズです。ペットボトルろ過器に雨水などを通し、一度沸騰させれば飲用水として活用できます。作るときにペットボトルの切り口で手を切らないように注意してください。
手作りペットボトルろ過器の作り方
- ペットボトルを半分に切る
- 飲み口にガーゼなどを詰め込む
- 飲み口を下にしてペットボトルの下部部分と重ねる
- ガーゼを詰め込んだ飲み口に向かって小石→ガーゼ→木炭→ガーゼ→小石の順に詰める
簡易水タンク
災害が原因で水不足に陥ると、自治体や消防などが給水を行います。ただ、せっかく給水の機会があっても、水を入れるタンクがなければ自宅へ水を運べません。そんなときには、段ボールと大きめのポリ袋で簡易的な水タンクを作りましょう。
水は食事だけではなく手洗い、うがいなどさまざまなシーンで使用します。万が一水タンクを買い忘れてしまった場合に備えて、段ボールとポリ袋を使用した簡易水タンクの作り方を覚えておきましょう。
手作り簡易水タンクの作り方
- ポリ袋を広げる
- 「1」を段ボールに入れる
- 水を入れる(給水時)
- 段ボールの下を小さくカット
- カットした部分からポリ袋を外側へ少し引っ張り出す
- 引っ張り出したポリ袋を1センチほどカットする(蛇口感覚で少しずつ水を出せる)
- 使用しないときには、カットした部分を洗濯ばさみで止めておく
スプーン
スプーンは非常時に不足しやすいことが特徴です。牛乳パックを使えば手作りできますので覚えておきましょう。少ない工程で、レンゲのような形のスプーンが完成します。牛乳パックが1本あれば全部で4つのスプーンが作れますので、いざというときのために覚えておきましょう。
手作りスプーンの作り方
- 牛乳パックを縦半分にカットする
- さらに縦半分に再度カットする(もとの大きさから縦1/4の形になる)
- 底を下にして、長いほうを持ちやすい長さ・太さにカットする
まとめ

いざというときのためにも防災グッズの準備は必要です。しかし、状況によっては必要なものが不足する場合も考えられます。防災グッズを自作する方法を知っておくことで、被災時に対処する一助になります。
年間1,000件以上の社内イベント・研修、地域イベントなどを支援する株式会社IKUSAでは、楽しく防災の知識を学べるイベントに関するサービスも多数提供しています。
詳しくは下記で防災・SDGsイベントサービスの資料を無料ダウンロードできます。
資料をダウンロードする\防災イベント・SDGsイベントのご相談はこちら/
防災・SDGsイベントのご相談はこちら防災に関するイベントサービスのご紹介
親子で楽しく防災に関するアクティビティ取り組む「防災ヒーロー入団試験」
資料をダウンロードするオンラインでも楽しく体験を通じて防災を学べる「おうち防災運動会」
おうち防災運動会の資料ダウンロードはこちら周遊型謎解きで親子で一緒に防災を学べる「災害都市からの大脱出」
資料をダウンロードする様々なアクティビティで楽しく防災を体験できる「防災フェス」
資料をダウンロードする
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
防災に役立つ豆知識が得られる記事はこちら!
防災の豆知識!知っておくと役立つ20の知識

1993年生まれ。栃木県在住。一児のシングルマザーライター。Web媒体・紙媒体にて、ジャンルを問わず多くのメディアで執筆。BtoB向け記事の他、ママ目線でのコラム執筆も手掛ける。専門家や起業家などへの年間インタビュー数200人を目標に、パワフルに活動中。

「やらないと」から「やってみたい」と思える防災へ。防災を楽しく学べるイベント「あそび防災プロジェクト」の発案者。防災運動会をはじめとした様々なサービスを考案。企業や自治体、商業施設での防災イベントの実施や、「世界防災フォーラム2019」「防災アイディアソン BOSAI Startups in Japan」へ登壇。「あそび防災プロジェクト」は2020年グッドデザイン賞を獲得した。








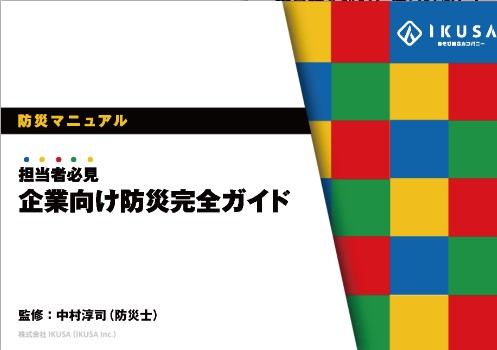





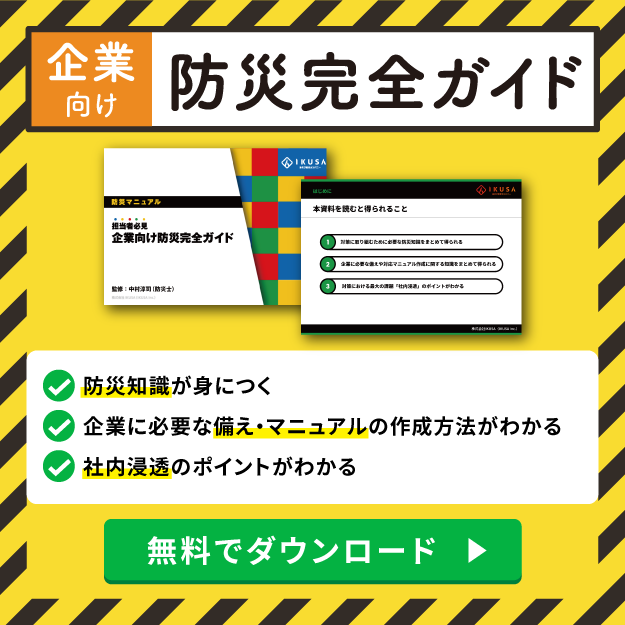


 粕谷麻衣
粕谷麻衣

 齋藤遥
齋藤遥

 萩 ゆう
萩 ゆう

 あそび防災情報局
あそび防災情報局



