自治体や企業にとって防災・減災対策は重要な課題となっており、防災・減災を目的としてICTサービスを活用する事例が増えてきています。
本記事では、防災・減災におけるICTサービスの活用事例や課題点などについて紹介します。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
ICTとは

ICTとは「Information and Communication Technology」の略称で、日本語に訳すと情報通信技術です。ICTを活用することで、迅速かつ効率的な情報伝達が可能になり、防災・減災のほか、医療・介護分野、教育分野、サイバーセキュリティ分野などでの利活用が推進されています。
政府も積極的にICTの効果的な利活用を推進
「私たちが抱える様々な課題(地域経済の活性化、社会保障費の増大、大規模災害対策等)に対応するため、社会の様々な分野(農林水産業、地方創生、観光、医療、教育、防災、サイバーセキュリティ等)におけるICTの効果的な利活用は不可欠である」として、政府・総務省も防災・減災におけるICTの利活用を推進しています。
防災・減災における例としては、「Lアラート(※)」の普及・啓発、「G空間情報(地理空間情報)」を利用した防災情報の高度化などが挙げられます。
※Lアラート……災害が発生した際に、放送局・アプリ事業者などのメディアを通じて情報を迅速かつ効率的に伝達する共通基盤。Lアラートは平成23年6月より運用されています。
各分野におけるICT活用

ICTは防災・減災に限らず、その他のさまざまな分野でも利活用されています。
ICT×医療・介護
医療・介護分野では、ICT活用を国が推進しています。ともに人材不足が大きな課題であり、医療・介護のサービス向上や従業員の労務改善などを目的として、ICTを活用することによる効率化が実現されています。
ICT×教育
教育分野でICTを活用することで、学生がより高い関心をもって授業に取り組めたり、効率的に授業を進められたりします。また、教員間の情報共有にも活かされています。
ICT×土木
土木分野では、ICTを活用することで、測量時間の短縮化や3次元データのさらなる有効活用などが実現されています。
土木分野では建設現場のプロセスにICTを導入して生産性や経営環境の改善を図るプロジェクト「i-Construction」が国土交通省により推進されています。
防災・減災分野におけるICT活用
防災・減災におけるICT利活用としては、以下が例として挙げられます。
- 緊急速報
- 安否確認
- 被害予測
- 情報収集
防災・減災においては、①「災害が発生した」、「災害の発生が予想される」などの災害情報を一刻も早く被災した地域住民の全員が確実に知れること、②家族や友人・知人、同僚・社員などの安否確認を迅速に行えること、③被害状況や今後の予測などの情報を得られることなどが重要です。
それらを実現するために、ICTが利活用されています。
参考:防災・減災等に資するICTサービス事例集|総務省(PDF)
防災・減災におけるICT活用の具体的な事例

ICTの基本情報に触れた上で、次に主な事例をいくつかピックアップして紹介します。
1.水位がチェックできる「河川情報システム」
岐阜県は他の都道府県と比べて、山間部の降水量が多い地域。県内の河川ごとに設置されている雨量計や水位センサーなどが計測したデータを収集し、リアルタイムで各河川の水位がわかる「河川情報システム」というICTを導入しています。
地図情報システムとも連携しており、地図データと組み合わせた統合的な表示ができるほか、スマートフォン版ではGPS機能と合わせて活用することができます。今では、多くの自治体でこのシステムが導入されています。
参考:岐阜県 川の防災情報
2.災害時でもつながる「防災Wi-Fi」
宮崎県小林市は霧島連山の噴火被害や大雨被害などを受けた地域であり、住民が災害に巻き込まれたケースもあります。これを踏まえて生まれたのが「防災Wi-Fi」です。
「防災Wi-Fi」はNTT西日本が2017年4月からサポートしているICTで、市役所や中学校、公園など避難場所を中心に40か所以上(2023年9月現在)、自由に使えるWi-Fiが設置されています。緊急時の連絡はもちろん、日常的にも、観光時いも使うことができます。
自治体による防災Wi-Fi環境の整備は総務省からも推進されており、必要が一部助成されることもあります。
参考:総務省|ICT利活用の促進|地方公共団体によるWi-Fi環境整備
3.緊急情報がすぐ確認できる「防災Infoひがしそのぎ」
災害時、メディアや国が伝える情報とともに、地元の状況に即した地元の情報も重要です。長崎県東彼杵町の場合はICTを活用して緊急情報を伝えています。
長崎県東彼杵町が行う「防災Infoひがしそのぎ」は、IP通信網やモバイル回線などを使って住民のスマートフォンや専用の受信機に災害に関する情報を同時に伝達。Jアラートとも連携しているため、全国的な緊急情報が起きてもすぐに確認できます。「防災Infoひがしそのぎ」には既読機能も搭載。いつメッセージをチェックしたのか確認できることから、住民の安否確認や高齢者の見守りにも活用できます。
参考:【NTT西日本】ICTを活用した地域密着型の防災情報発信~防災Infoひがしそのぎ~ – 通信・ICTサービス・ソリューション
4.地域に一括送信できる「エリアメール」
「エリアメール」は、NTTドコモが提供しているICTです。特定の地域にある携帯電話に対して緊急情報を一斉送信するというもので、気象庁や自治体が発する緊急地震速報や津波警報、避難指示を含む「Lアラート」を受け、対象地域のみに避難指示や避難所開設情報を届けます。
5.災害時の道路規制状況が見える「しずみちinfo」
2011年の東日本大震災やその後の大型台風の際、災害情報サイトのアクセスが込み合ったことがあり、災害対応に遅れが生じるおそれがあったため、静岡市では職員も住民も地域の中でどの道は通行可能で、どの集落が孤立しているか、などがリアルタイムでわかるクラウドサービス「しずみちinfo」を開始しました。
クラウド上にデータがあるのでネット環境があれば誰でも閲覧ができます。
防災・減災におけるICTの課題

防災・減災において、ICTは完全なものではなく、ICTを活用する際にシステムに関する理解が必要なものも少なくないなどの課題があります。
例えば、日本において発生数の多い地震災害や水害などでは、停電やシステム自体の被災などにより、電話やインターネットが利用できなくなる場合があります。そうした状況ではICTが機能しない可能性が想定され、通信環境を確保する手法・技術が必要です。
また、迅速かつ効率的なICTが利活用されていても、「被災者がそれを理解していない」、「認知していない」などにより、有効活用できない場合もあります。自治体や企業はICTを利活用するだけでなく、地域の人々に広く伝えていくことが求められます。
まとめ
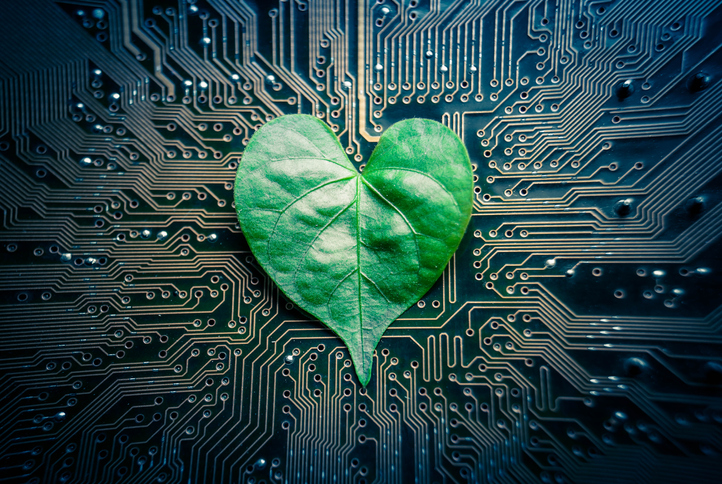
本記事では、防災・減災におけるICTの活用事例や課題などを紹介しました。ICTを活用することにより、さまざまな分野の生産性向上・効率化などを実現することができます。今後もさらなるICT活用による防災・減災への取り組みが期待されます。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!




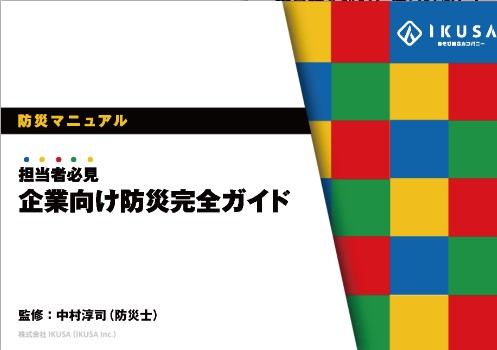





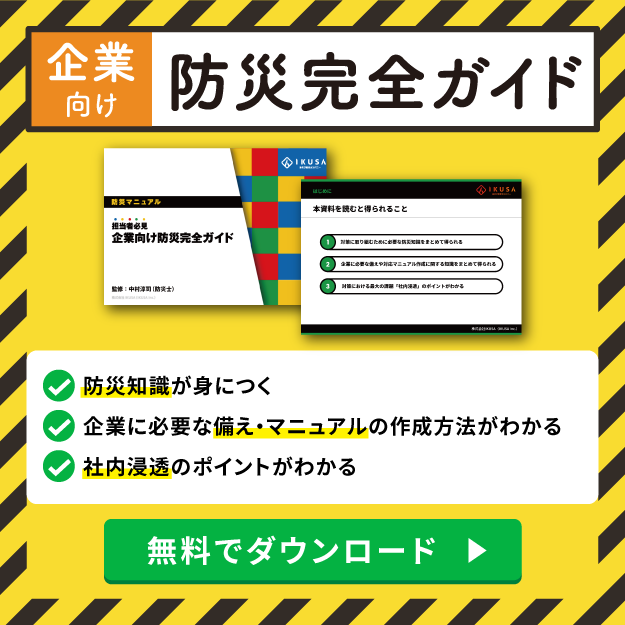


 粕谷麻衣
粕谷麻衣
 粕谷麻衣
粕谷麻衣


 JJ
JJ





