
防災について学ぶことで知識を定着させたり、自分ゴト化させたりするには、実際に体験してみることが重要です。
本記事では、地震体験、消火体験などができる全国(北海道・東北・関東・北陸・東海・関西・中国・四国・九州・沖縄)の防災体験施設を20件ピックアップし、特徴や施設情報を紹介します。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
北海道・東北の主な防災体験施設4選
まずは北海道・東北の防災体験施設を4つ紹介します。
1.札幌市民防災センター
札幌市民防災センターは、消火体験や地震発生時の避難体験など、被災時にどのような行動をすればいいのかについて学べる防災体験施設です。入館料は無料で、基本的には予約は不要ですが、10名以上の団体見学をする場合は事前予約が必要です。
施設情報
住所 | 札幌市白石区南郷通6丁目北2-1 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 年末年始及び第1・第3月曜日(祝日の場合は翌日) |
参考:札幌市民防災センター
2.岩手県立総合防災センター
岩手県立総合防災センターは、災害発生の仕組みを学べる「防災展示室」や、震度4〜7の揺れを体験できる「地震体験室」、煙の中での避難体験ができる「暗闇・煙体験室」など、さまざまな展示物・体験設備がある防災体験施設です。
また、多様な防災セミナーを開催していることも特徴です。基本的な心構えを学ぶ「防災体験コース」、避難器具の使用や誘導方法を学ぶ「避難コース」、さらに小さなお子様向けの「幼児コース」もあります。防災セミナーへの参加には事前に予約が必要です。
施設情報
住所 | 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目2番2号(県消防学校隣接) |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合開館) |
参考:岩手県立総合防災センター
3.KIBOTCHA
「KIBOTCHA」は、東日本大震災で大きな被害を受けた野蒜小学校の校舎を活用した防災体験施設です。野蒜駅から歩いて徒歩10分ほどですが、無料送迎サービスもあります。「KIBOTCHA」ではバーベキューやグランピング、サンドアートなどを体験できますが、そのなかの一つとして防災教育キャンプがあります。
「KIBOTCHA」の防災教育キャンプは、プログラムによって内容が異なります。例えば社員研修向けのプログラムでは、防災食の実食や防災マップの作製などを体験できます。
施設情報
住所 | 宮城県東松島市野蒜字亀岡80番 KIBOTCHA |
入館料 | 利用施設による |
電話番号 | |
休館日 | 火曜日 |
4.山形県防災学習館
山形県防災学習館には、過去の災害記録を実際に映像で見ることのできる「防災シアター」や、消防団員の活動内容をアニメと実写の両方で学べる「山形県の消防活動」などがあります。
体験コーナーもバラエティに富んでいて、訓練用の消火器を使用した消火訓練、訓練用の人形を使用した応急手当ての訓練など、災害時に役立つ知識を身につけることができます。
施設情報
住所 | 山形県東田川郡三川町大字横山字堤27-1 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合開館)、祝日の翌日、年末年始 |
関東の主な防災体験施設5選
次に関東の防災体験施設を5つ紹介します。
5.そなエリア東京
そなエリア東京は、東京臨海広域防災公園の中にある防災体験施設です。首都直下型地震の被害想定に基づいた防災知識を学ぶことができます。そなエリア東京にはさまざまなコーナーがあります。例えば「東京直下72hTOUR」では、体験施設利用者は首都直下型地震が起きた場合をイメージして作られたジオラマの中を歩きながら、貸し出されたタブレットに出題されるクイズに解答します。地震が起きた直後から避難するまでの過程を体験できるため、いざというときにどのような行動をとればいいのかを学習できます。
施設情報
住所 | 東京都江東区有明3丁目8番35号 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 月曜日、年末年始及び臨時休園日 |
参考:防災体験学習(そなエリア東京) | 東京臨海広域防災公園
6.池袋防災館
池袋防災館は、1時間40分の防災体験ツアーで地震や消火などについて体験しながら学べる防災体験施設です。50分のショートコースもあるため、短時間で防災の知識を深めたい場合にもおすすめです。池袋駅から歩いて5分ほどの場所にあり、アクセスが良いことも特徴です。
また、池袋防災館ではナイトツアーも行われています。毎週金曜日に開催されており、夜間の発災を想定した各種災害の体験ができます。
施設情報
住所 | 東京都豊島区西池袋2丁目37番地8号 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | 03-3590-6565 |
休館日 | 毎月第1火曜日、第3火曜日及び第3火曜日の翌日、年末年始 |
参考:池袋防災館|各施設のご案内|防災館 東京消防庁 都民防災教育センター
7.東京消防庁本所防災館
東京消防庁本所防災館は、地震の揺れの体験、初期消火や応急救護、火災の煙からの避難要領など、防災に関する知識や技術を学べる防災体験施設です。1〜4階まであり、各階に展示・見学コーナーがあります。
10名以上での団体利用は予約が必要ですが、個人利用なら予約不要で見学することができます(空きがある場合)。また、季節ごとにイベントを開催しており、親子で楽しめる工夫がされています。
施設情報
住所 | 東京都墨田区横川4-6-6 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週水曜日・第3木曜日、年末年始 |
参考:本所防災館|各施設のご案内|防災館 東京消防庁 都民防災教育センター
8.東京都北区防災センター(地震の科学館)
東京都北区防災センター(地震の科学館)は、展示ホールの見学防災体験などをすることができ、国の「防災基地モデル建設事業」の一環として設立された歴史ある防災体験施設です。
地震体験コーナーでは、関東大震災や阪神淡路大震災、東日本大震災など、過去に起こった災害を再現し、その揺れを体感することができます。
また、消火器を使った訓練、AEDを利用した訓練、ロープワークなど、さまざまな体験ができます。予約が必要な場合もあるため、公式サイトなどで確認してください。
施設情報
住所 | 東京都北区西ケ原2-1-6 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日(国民の祝日・休日の場合は開館し、直後の平日に振替休館)・国民の祝日(ただし土曜日の場合は開館)・年末年始 |
9.神奈川県総合防災センター
神奈川県総合防災センターは、突然の災害でも迅速に対応できることを目指して地震や風水害、火災などの防災について学べる防災体験施設です。風水害体験コーナーでは風速30m/秒の強風を体験することができます。。また、心肺蘇生法や避難所での生活体験などができるコーナーも用意されています。
神奈川県総合防災センターは予約不要かつ無料で入館できますが、10名以上の団体で利用する場合は予約が必要です。
施設情報
住所 | 神奈川県厚木市下津古久280 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始 |
北陸・東海の主な防災体験施設4選
次に愛知県や岐阜県、富山県などが含まれる北陸・東海地域の防災体験施設を4つ紹介します。
10.名古屋市港防災センター
名古屋市港防災センターは、愛知県名古屋市の港区にある震度7の地震体験や煙避難体験などができる防災体験施設です。また、1959年に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風の3D映像も視聴できます。そのほか、ミニ消防車との記念写真コーナーや防災トークなども用意されています。
予約せずに無料で入館できますが、体験ツアーの案内や特別講座の場合は予約が必要です。
施設情報
住所 | 愛知県名古屋市港区港明一丁目12-20 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 月曜日(祝日の場合は次の平日)、第3水曜日 |
11.四季防災館
四季防災館は、四季をコンセプトとしており、季節性のある災害への対策を行ってきた先人たちの知識を紹介している防災体験施設です。地震体験や119通報体験、高齢者等助け合い体験、雪が降る地域ならではの雪崩体験ができます。
基本的には予約不要で入館できますが、10名以上の場合は7日前までに予約する必要があります。
施設情報
住所 | 富山県富山市惣在寺1090-1 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日、年末年始、その他臨時休館日 |
参考:四季防災館
12.静岡県地震防災センター
静岡県地震防災センターは、「知る」「備える」「行動する」をコンセプトに、豪雨や噴火、土砂災害など多様化する災害に合わせた展示を行っている防災体験施設です。
地震・津波を学ぶ1F、メカニズムから風水害や火山災害を学ぶ2F、学習・研修スペースの3Fという構成になっており、夏休みや冬休みなどには防災イベントも開催しています。
基本的に個人、団体問わずツアー制となっているため、予約する必要があります。
施設情報
住所 | 静岡県静岡市葵区駒形通5-9-1 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日、年末年始 |
13.長岡震災アーカイブセンターきおくみらい
長岡震災アーカイブセンターきおくみらいは、2004年10月23日に発生した、新潟県中越大震災の展示を主とする防災体験施設です。地震により孤立した地区の路上に描かれたSOSメッセージを原寸大で床に再現したデザインや、震災発生後の航空写真と詳細な被害状況が分かるMAP、実際の映像や被災した方へのインタビュー映像をみることのできるシアターなどが展示されています。
また、有料のガイド付き研修ツアーや、小学生から大人にまで年齢にあわせた研修プログラムもあります。施設見学には予約が必要です。
施設情報
住所 | 新潟県長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト2階 |
入館料 | ガイドなしの見学は無料、その他コースにより有料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12/29-1/3) |
参考:長岡震災アーカイブセンター きおくみらい ― 私たちの10月23日を伝えるために。 ―
関西・中国・四国の主な防災体験施設5選
次に関西・中国・四国の防災体験施設を5つ紹介します。
14.京都市市民防災センター
京都市市民防災センターは、地下空間へ浸水の恐ろしさを伝える4Dシアターや消防ヘリコプターの実物展示なども用意され、キッズコーナーもある防災体験施設です。さまざまな防災体験を通じて防災意識や活動能力を高めることを目指しています。
基本的には予約不要ですが、10名以上の場合は予約が必要です。京都市内の団体は4ヶ月前、市外団体の場合は3ヶ月前から予約可能です。
施設情報
住所 | 京都府京都市南区西九条菅田町7番地 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 月曜日、第2火曜日、年末年始 |
15.あべのタスカル 大阪市立阿倍野防災センター
あべのタスカル 大阪市立阿倍野防災センターは、「おおさか防災情報ステーション」や「タスカルシアター」、「キッズしょうぼうパーク」などのコーナーがある防災体験施設です。
体験コースもあり、専任のスタッフに案内してもらえます。数種類のコースが用意されており、所要時間やコース内容などをチェックして選ぶといいでしょう。
施設情報
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 水曜日、毎月最終木曜日、年末年始 |
16.広島市総合防災センター
広島市総合防災センターは、さまざまな防災研修を行う防災体験施設です。具体的には、市民研修や子ども研修、事業所研修などがあります。また、防火管理者の資格取得講習も広島市総合防災センターで行われています。
地震体験や降雨体験、消火体験などが用意されており、楽しく防災知識を身につけることができます。
施設情報
住所 | 広島県広島市安佐北区倉掛二丁目33番1号 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 日曜日、祝日、振替休日、8月6日、年末年始(12月29日~1月3日) |
17.徳島県立防災センター
徳島県立防災センターは、地震や暴風の体験ができるだけではなく、心肺蘇生や基本的な止血方法まで学べる防災体験施設です。徳島県板野郡にある防災啓発施設としての一面と災害対策活動の中核拠点としての一面という2つの顔を持っています。入館料はかからず、10名未満の場合は予約が必要ありません。
施設情報
住所 | 徳島県板野郡北島町鯛浜字大西165 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)、第1火曜日(祝日の場合は開館)、年末年始(12月28日から1月4日まで) |
18.岩国市防災学習館
岩国市防災学習館は、煙の充満する中を避難する煙避難体験や、消火体験、地震体験、119番通報の体験ができる防災体験施設です。
10名以上のご利用は事前の予約が必要ですが、基本的には自由に見学できます。駐車場も無料で利用することができます。
施設情報
住所 | 山口県岩国市愛宕町1丁目4番1号 いわくに消防防災センター内 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
九州・沖縄の主な防災体験施設2選
九州・沖縄にもさまざまな防災体験施設がありますが、その中から2つ選出して紹介します。
19.福岡市民防災センター
福岡市民防災センターは、地震や台風などの防災について体験できる防災体験施設です。1時間の体験コースが用意されており、子供だけではなく大人も学ぶことができます。
入館料は無料ですが、月曜日と毎月最終の火曜日が休館日であることには注意しましょう。予約は必要ありませんが、他の施設と同じく10名以上の来館は事前予約が必要となります。
施設情報
住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜1-3-3 |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 月曜日、毎月最終火曜日、年末年始(7月21日~8月31日は毎日開館) |
20.沖縄市防災研修センター
沖縄市防災研修センターは、「災害を知る、災害を自ら体験する、災害に備える」を基本方針として掲げ、災害の危険性を伝える3Dシアターや防災関連の情報が検索できる防災検索テーブルなどが用意されている防災体験施設です。
見学する際には予約が必要で、土日に利用する場合は1ヶ月前までに予約する必要があります。
施設情報
住所 | 沖縄県沖縄市美里5丁目29番1号(沖縄市消防本部内) |
入館料 | 無料 |
電話番号 | |
休館日 | 毎週水曜日、国民の休日、慰霊の日、年末年始 |
防災体験なら「あそび防災プロジェクト」もおすすめ!
もし近くに施設がない場合や施設へ行く時間が無い場合は、「あそび防災プロジェクト」を検討してみましょう。「あそび防災プロジェクト」は株式会社IKUSAが実施する防災体験であり、以下のようなコンテンツを用意しています。
防災ヒーロー入団試験
「防災ヒーロー入団試験」は、頭と身体を使って防災を学ぶアクティビティです。家族向けのイベントや教育機関のイベントに向いており、「防災スリッパ作り」や「防災ウォークラリー」などさまざまな種目が用意されています。
おうち防災運動会
もしオンラインで防災に関して学びたいのであれば、「おうち防災運動会」がおすすめ。オンラインで楽しみながら防災について学べるプログラムが用意されており、運動会らしい競争要素も多いです。アクティビティとしても楽しめるため、オンラインでの社内イベントを検討している方にもぴったりです。
おうち防災運動会の資料ダウンロードはこちらおうち防災運動会のお問い合わせはこちら
防災謎解きオンライン
「防災謎解きオンライン」は謎を解きながらオンラインで防災を学ぶアクティビティです。参加者は災害に直面していているという設定で、ストーリーに沿って謎を解き、ミッションをクリアしていきます。
例えば「崩れゆく会議室からの脱出」というストーリーの場合は、巨大地震により会議室の耐震システムが破損したという設定の中で、次の大きな揺れが発生するまでに、謎を解き耐震システムを復旧させるというミッションをクリアしていきます。
制限時間内にすべての謎を解ききるには、メンバー同士のコミュニケーションが必要不可欠。リーダーシップや役割分担の大切さを学ぶことができるので、防災の知識を得るだけでなく、チームビルディング研修やリーダーシップ研修にも活用できます。
防災謎解きの資料をダウンロードする防災・SDGsイベントのご相談はこちら
防災コンセンサスゲーム
「防災コンセンサスゲーム」は災害時の対応をテーマとしたコンセンサスゲームです。オンラインで実施することができます。参加者は災害に巻き込まれたという設定の中で、どのように対応するかをチーム全員で話し合い、合意形成していきます。
首都直下型の地震がもし起こると東京都では517万人の帰宅困難者が発生すると言われています。「帰宅困難サバイバル」というストーリーの場合は、この状況をイメージし、災害が起きた際の適切な対処や行動の選択肢を理解し、発災した際の対応を楽しく学んでいきます。
災害時の対応が学べるだけでなく、全員で合意形成をしていく課程で、論理的思考力や相手の話を聞く力、協調性、価値観の違いとコミュニケーションの重要性を学ぶことができ、チームビルディングにもつながります。
防災コンセンサスゲーム「帰宅困難サバイバル」の資料をダウンロードする防災・SDGsイベントのご相談はこちら
防災運動会
「防災運動会」は運動会に防災知識を取り入れた新しい運動会です。運動会としての楽しさを残しながらも、防災に関する知識や知恵を身につけ、自分で助かる・他人を助けることの大切さを学べます。
防災を「事前準備/災害発生/発生直後/避難生活/生活再建」という5つのフェーズに分割し、それぞれのフェーズ毎に競技を行うので、防災の段階に応じた知識を身につけられるのも特徴的です。
競技内ではチームメンバーで力を合わせていく必要があるため、チームビルディングにもつながります。
防災運動会の資料ダウンロードはこちら防災運動会のお問い合わせはこちら
万が一に備えて防災を学ぼう!

今回は、防災体験ができる全国の主な施設をメインに紹介しました。防災体験ができる施設は日本全国にあります。また、上記で紹介したようなオンラインで防災を学ぶプランもありますので、人数や場所などを考慮して決めてみてください。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
============================
(Wordpressのメタディスクリプションを以下に修正してください)
本記事では、地震体験、消火体験などができる全国(北海道・東北・関東・北陸・東海・関西・中国・四国・九州・沖縄)の防災体験施設を20件紹介します。
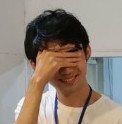
旅行系からビジネス系に至るまで、幅広いジャンルを執筆するWebライター。国内外を旅しながら、記事を書いています。




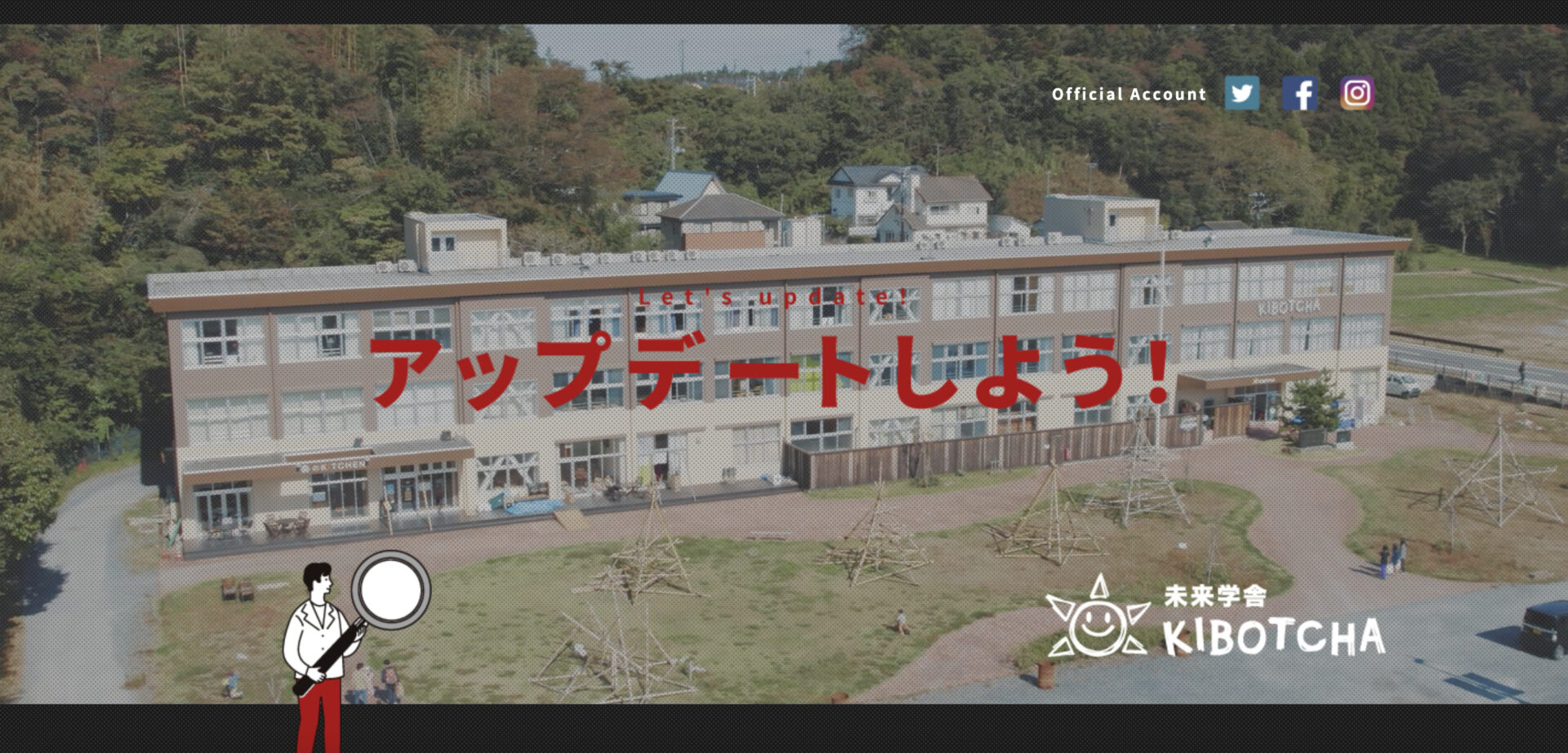





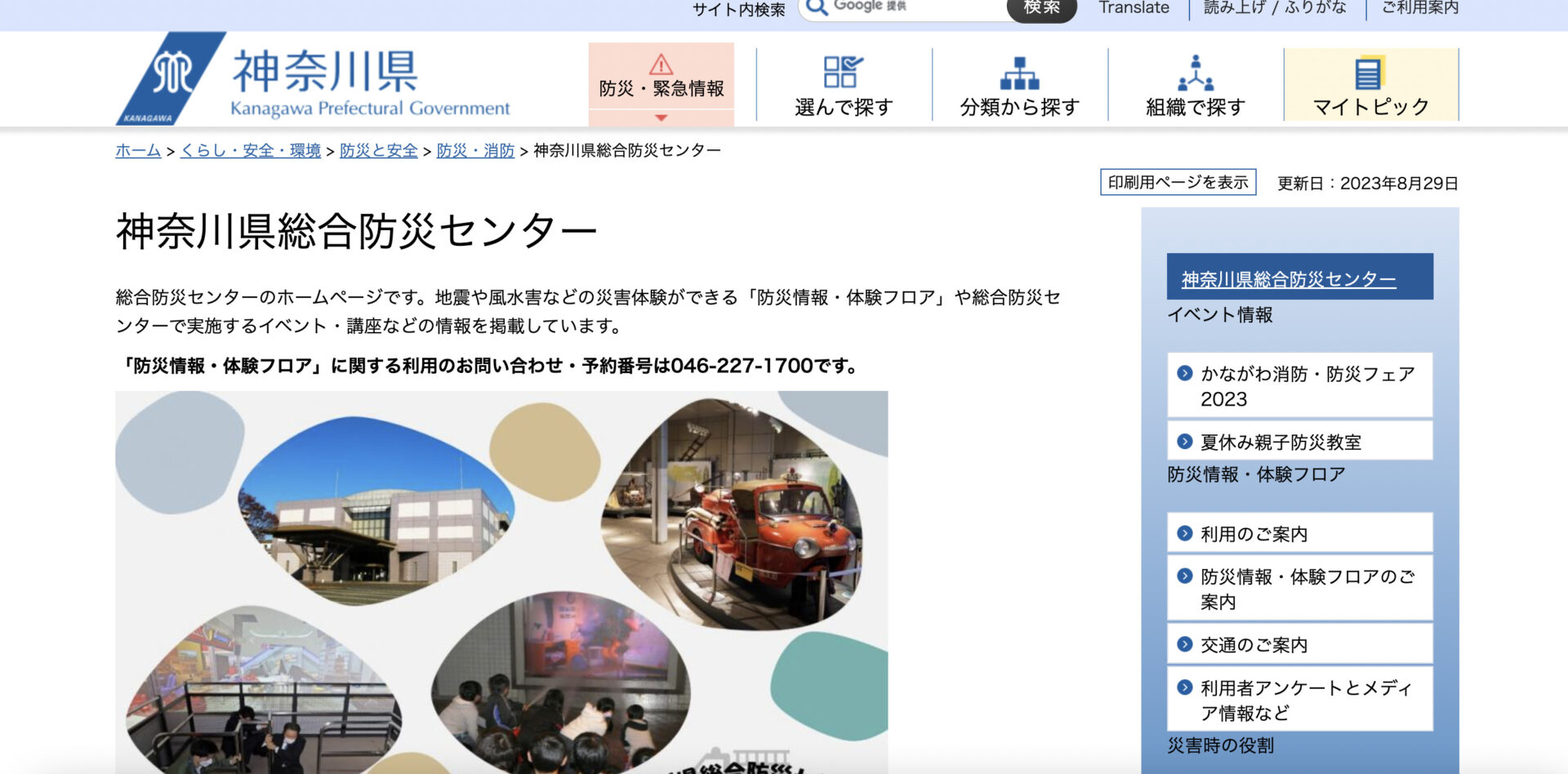


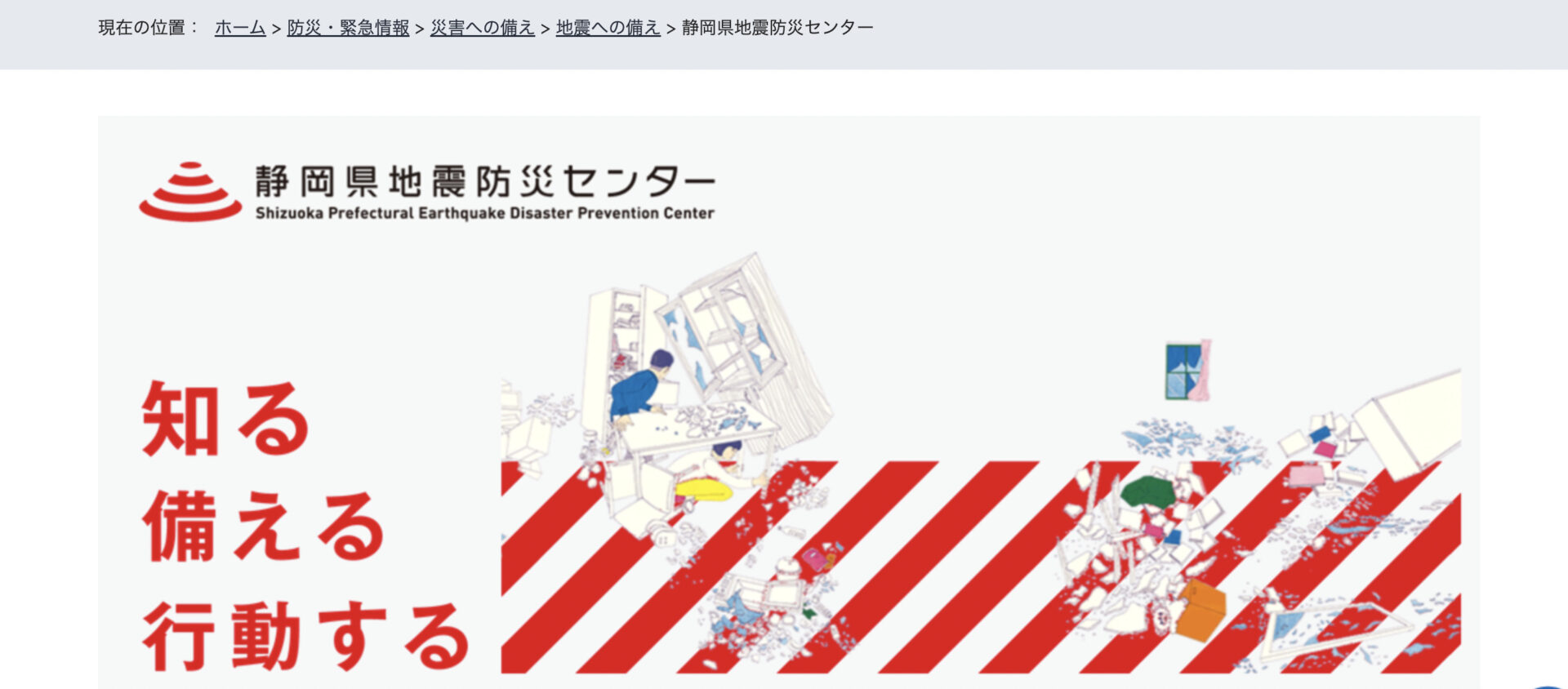











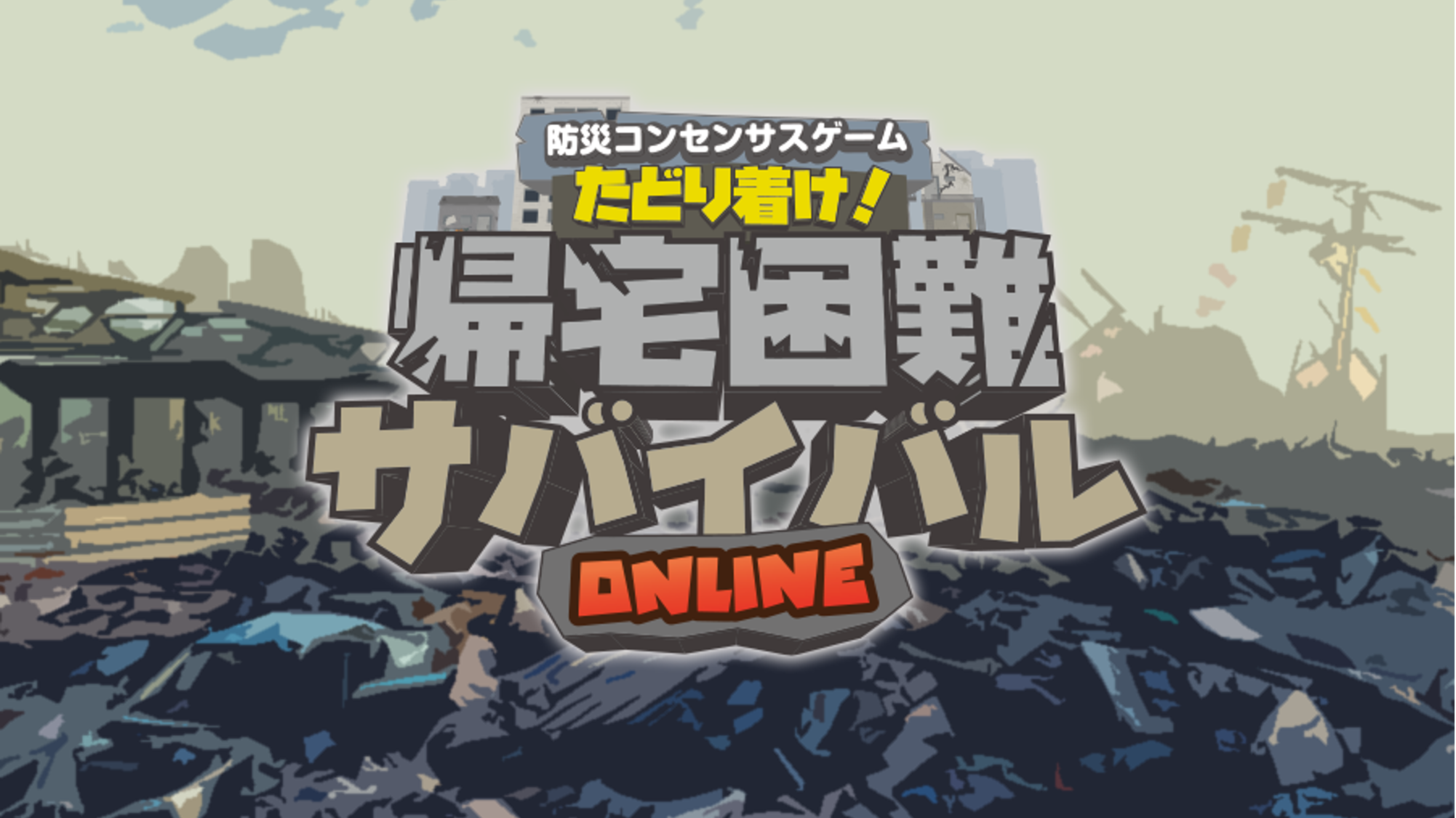


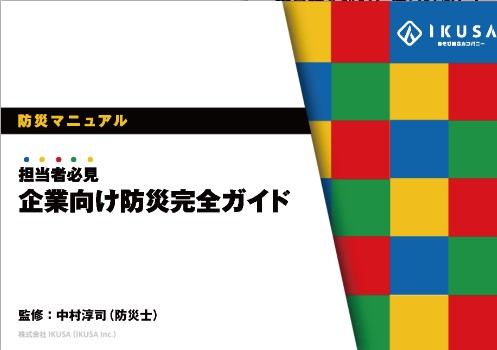





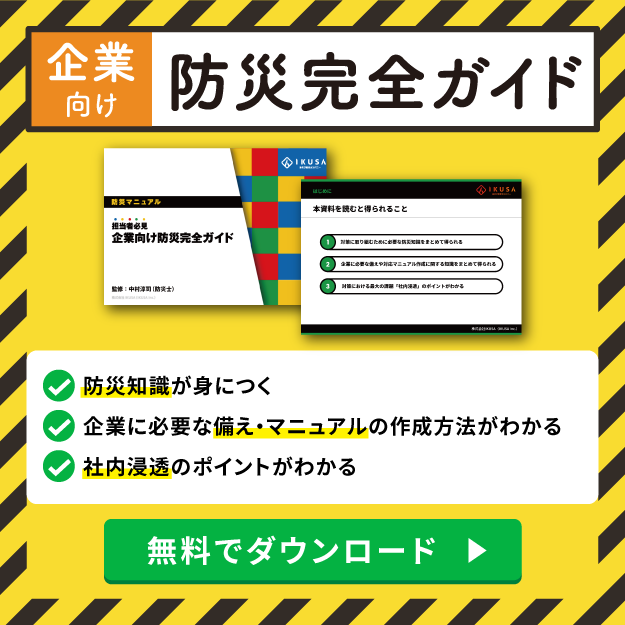


 あそび防災情報局
あそび防災情報局
 萩 ゆう
萩 ゆう
 粕谷麻衣
粕谷麻衣

 あるぱか
あるぱか





