地震や津波、台風による水害、火災…災害大国である日本では、災害による被害をゼロに抑えることはできません。万が一のときの被害を最小限に抑え、防災に強い地域を作るために、防災における地域コミュニティの必要性が高まっています。
地域によっては近所付き合いが希薄だったり、防災への意識がまだ低かったり、過疎の地域では行動が起こしづらかったりと、その地域特有の課題を抱えている場合もあります。
本記事では、地域コミュニティの必要性や防災活動内容の事例について詳しくご紹介します。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
⇒解説資料のダウンロードはこちらから
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
防災には「地域コミュニティ」の存在が重要

地域コミュニティの必要性の背景にあるのは、「共助」という考え方です。東日本大震災など大災害の発生時、自衛隊や民間救助隊の応援が不可欠になりますが、インフラや交通網が遮断された状況では、救助の手が届かない場所が生じてしまうことは避けられないでしょう。
発生時からその直後は、まず自分や家族の生命を守る「自助」に務めることを大前提です。その後、自衛隊などの救助が来るまでの間、同じ地域の住民同士でお互いに助け合う「共助」の精神が必要になるのです。特に水害や土砂崩れなどが起きた場合、生命のリミットとして知られる72時間、地域住民同士で声掛けや協力をし合うことで、助けられる生命が少なくありません。
いずれくると言われている南海トラフ地震や、全国各地で発生する豪雨災害などの、今後のためにできる備えとして、防災のために地域コミュニティでの取り組みは必要不可欠となっています。
また、2011年の東日本大震災以降、国の防災対策の指針を示す「防災対策基本法」が年々改訂されていますが、2013年の改訂では、市町村地域防災計画の一部として、地区居住者等が行う自発的な防災活動に関する計画(地区防災計画)が明確に位置付けられました。この点から見ても、今後の防災対策には地域コミュニティの存在が欠かせません。
参考:最近の主な災害対策基本法の改正 : 防災情報のページ – 内閣府
地域コミュニティを形成するメリット

具体的に、防災のために地域コミュニティを形成するとどんなメリットがあるのでしょうか。
共助力向上に繋がる
まず挙げられるのが共助力の向上です。地域の住民同士がお互いに関係性が築けていれば、助け合いによって命を守ったり、精神的に支え合ったりという共助が可能になります。
特に災害は地域によって危険性に差があり、地域住民同士での迅速な対応は他の救助よりも効率がいい場合もあります。どこに高齢者がいるのか、どの避難経路が最適か、など、地域コミュニティーの中で情報を共有することが防災に繋がります。
現場での情報共有が円滑になる
防災のための地域コミュニティが機能していることで、スピーディーな情報収集と円滑な情報共有が可能になります。特に大災害発生時は混乱しがちですが、お互いに危険箇所を認識していたり、防災訓練にも力を入れていれば、いざというときに素早く判断・行動へ移しやすくなります。
地域活性化に繋がる
最近では、地元企業が地域コミュニティと連携し、備蓄品を提供したり、施設を開放したりという事例も増えてきました。その活動の源泉となるのは、地元への愛着心。自分たちの地域は自分たちで守る、という機運が高まれば、さらに地域の防災は実効性のあるものとなるでしょう。
地域コミュニティ強化のための防災活動
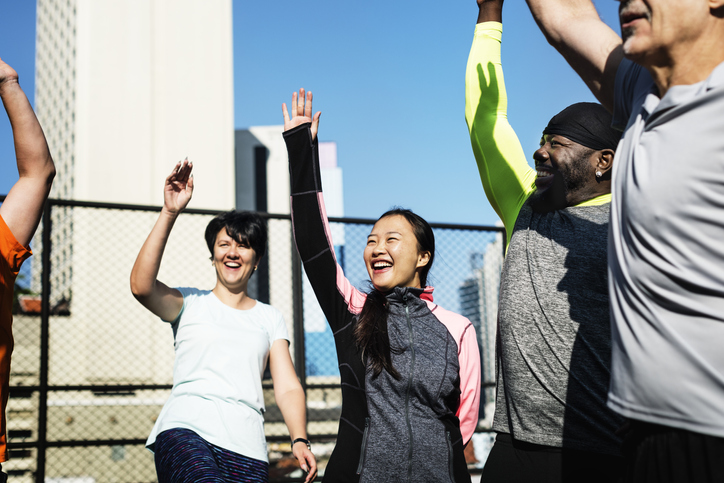
地域コミュニティ強化のために、国内でさまざまな活動が行われています。その取り組み例を紹介します。
防災イベントの実施
現場で災害を疑似体験したり、災害が発生したときの状況や取るべき動きを学んだりと、防災意識を高めるイベントが多数行われています。
防災に必要な知識を得るだけでなく、共助の必要性について触れられるのも大きなメリットです。助け合うことや地域コミュニティの必要性を学べば、日頃の過ごし方にも変化が起こるでしょう。地域に特化した防災イベントでは、例えば海沿いの自治体であれば津波について、山が近い場所であれば土砂崩れについてなど、地域ごとのハイリスクな災害について触れることができ、地域全体で防災について考えることができます。
兵庫県西宮市では、2020年にオンラインで防災を学ぶ「おうち防災運動会」が行われました。
おうち防災運動会は、Zoomなどのビデオチャットツールで行う、防災をテーマにした運動会です。家の中の非常食を探す「おうち探検!非常食探索トライアル」やVTRをみて防災上の間違いを探す「防災間違い探しONLINE」などの競技を通し、楽しみながら防災を学ぶことができます。
家にいながら運動を楽しむことができ、家族ぐるみで参加しやすいので、お子様から大人まで、一緒に防災を学ぶことができます。
詳細はこちらの記事をご覧ください▼
オンラインで防災を学ぼう!西宮市「おうち防災運動会」開催レポート
おうち防災運動会の資料ダウンロードはこちらおうち防災運動会のお問い合わせはこちら
自治体単位で行うイベントとしては、「防災フェス」もおすすめです。

「防災フェス」は、謎解きやワークショップで楽しみながら防災知識を身に付けられるイベントです。実際の災害時の展示物や講演会などを行ったり、地域の状況に沿った内容で開催することができ、実際に大阪府堺市港区の「みなみフェスタ」事例などもあります。子どもから大人まで楽しめる内容で、地域コミュニティを形成するきっかけに最適です。
詳細はこちらの記事をご覧ください▼
【アンケート結果公開】堺市南区にて「みなみ防災フェスタ」を開催!体験型ワークショップで楽しく防災を学ぼう!防災・SDGsイベントのご相談はこちら
ハンドブック作成・改定
地域向けに防災用ハンドブックを作成・配布している地域は多数ありますが、定期的に内容を改定したり、新しく作成したりするケースは少ないのが現状のようです。災害情報は常に変化しています。数年前に作成したハンドブックの内容が、現在でも同じであるとは限らないため、ハンドブックは作成しっぱなしで終わるのではなく、定期的に近年の気象状況や、災害の被害などを見直して新しく作り直す、一部を改定して再配布をするといった対応が必要です。
また、ただ配布して終わるのではなく、公民館や集会所など、住民が頻繁に行く場所にも置き、普段から目に入るような状況にしておくとより効果的です。
防災セミナー、勉強会
防災の知識も、日々新しくなっています。地域住民に防災に関する講演を聞いてもらったり、災害時の対応について話し合いをする場を設けることが大切です。
ユニークな例として、鹿児島県始良市の取り組みがあります。始良市では小学校校区を範囲とし、校区コミュニティ協議会を設置しました。地域住民がウォーキングに参加、歩きながら見つけた市のよいところと危険な箇所を確認して、それをもとに防災マップを作成しました。
住民自ら地域のことを再確認したことで、防災意識の向上につながりました。
参考:地域の絆と災害に強い地域づくり 施策事例集 – 福井県(p22)
防災コンテスト
地域住民一体となってコンテストに参加してみると、より「災害に備えよう」、「非常時には助け合おう」という意識が高まるかもしれません。
ほかにもさまざまな組織が開催していますが、消防庁では平成8年から「防災まちづくり大賞」として、防災に関する取り組みを表彰しています。どのような組織・団体でも応募することができ、町内会の立ち上げた防災会も受賞しています。
一例として、令和3年度には島根県の西郷中町町内会連合会が、楽しく防災を学べるイベントの企画や講師を招いた勉強会、定期的な設備点検を自主的に行なって文部科学大臣賞を受賞しました。
参考:防災まちづくり大賞 | 地域防災を支える自主防災組織等の育成 | 総務省消防庁
過去の災害から見る地域コミュニティが機能した例

実際の災害時でも、地域コミュニティが機能した事例はたくさんあります。ここからは、過去の災害で地域コミュニティが機能した例をご紹介します。
台風被害
宮崎県 諸塚村
令和4年度に発生し、大きな被害をもたらした台風14号での事例です。面積の95%を森林が占める小さな村では、予め地形に対応したハザードマップと支援が必要な人のリストを作成。また、公民館単位で1年に1度の避難訓練も実施していました。
集落が点在しているという村の状況を鑑みて16の自治公民館がそれぞれ組織運営をしして、自助・共助を進める取り組みにより、離れたところに住んでいる人も逃げ遅れることのない体制を作っており、「諸塚方式」と呼ばれています。
参考:令和4年度の災害を中心とした事例集 (災害対応事例集)|総務省消防庁
群馬県南牧村
平成19年度の台風9号による豪雨災害の事例です。山間部に位置し、高齢者が多い限界集落である南牧村では、大雨時に区長が地域の見回りや、住民への状況伝達を繰り返し、危険だと判断した際には避難を促すなど、非常に積極的なコミュニケーションをとっていました。
最初は「大したことにはならないだろう」と考えていた住民もいたとのことで、区長の声かけによって意識が高まり、共助に繋がりました。コミュニケーションによって多くの人命が救われた例です。
参考:地域コミュニティ特性に応じた豪雨災害対応の重要性 片田敏孝
東日本大震災
岩手県大船渡市 生形自主防災組織
チリ地震津波を経験した大船渡市では、平成7年に公民館役員の提案で自主防災組織を立ち上げました。普段から「緊急時要援護者マップ」を作成し、住民がそれぞれ高齢者の担当となって、避難時には担当の高齢者へも声をかける仕組みを作りました。また、毎年5月に避難、炊き出し、救出・搬送、消火の訓練や、児童へ津波体験談を話す日を設けています。防災用品も全世帯に配布して災害に備えていました。
震災時には、発生直後から避難誘導、避難所運営を行い、ほとんどすべての住民がスムーズに避難することができました。普段から災害に備える雰囲気づくりが、実際に役立った例です。
宮城県仙台市 鈎取ニュータウン町内会
阪神・淡路大震災の発生後から、「自分たちの町は自分で守る」を念頭において活動しています。防災に関する地域のオリジナルキャラクターを作成し、他地方で地震が発生した直後に防災訓練を実施。また、麻雀クラブ、仙台市内の公園の草刈り、夏祭り、新年会など、地域で仲間意識を持たせる場を積極的に提供し、地域コミュニティを形成していました。
地震発生時には住民自らが災害本部立ち上げ、避難所運営に対応しました。さらに町内会では「黄色い旗」を使った安否確認方法を導入しており、地震から約35分で全世帯に負傷者がいないことを確認し、在宅していなかった人からも自主的に安否連絡がありました。住民と地域との信頼関係があったからこそ、スムーズな対応が可能になりました。
千葉県浦安市海風の街自治会
海風の街自治会は32棟のマンション住民によって、平成7年に立ち上げられました。平常時には震災時の行動についてまとめたガイドや、無事であることを玄関外に貼り付けて知らせる「安否確認カード」を配布したり、マンションの管理組合や消防署とも連携して、年に2回の防災訓練を行なっています。安否確認から防災講習、AED使用、救命・看護、炊き出しの訓練など、幅広い備えを行なっていました。また、花植え活動やラジオ体操、バス旅行、クリスマスイベントなど、住民同士の交流の場も積極的に提供していました。
被災時には、安否確認はもちろん飲料水・簡易トイレの配布を行い、発生2週間後までに仮設トイレを設置したり、給水車レンタルなどでスムーズにインフラを確保しました。
参考:東日本大震災における 自主防災組織の活動事例集|総務省消防庁
まとめ

災害発生時、地域コミュニティの共助は不可欠です。災害自体はなくせませんが、被害を最小限に食い止め、災害発生前の日常に1日でも早く戻るためにも、平常時から備えておく必要があります。
まだ十分にコミュニティが形成できていない地域は、これを機にコミュニティのあり方などを考える必要があるでしょう。地域の防災に関わったことがないという場合は、ぜひ今一度コミュニティ形成に目を向けてみてください。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!

「やらないと」から「やってみたい」と思える防災へ。防災を楽しく学べるイベント「あそび防災プロジェクト」の発案者。防災運動会をはじめとした様々なサービスを考案。企業や自治体、商業施設での防災イベントの実施や、「世界防災フォーラム2019」「防災アイディアソン BOSAI Startups in Japan」へ登壇。「あそび防災プロジェクト」は2020年グッドデザイン賞を獲得した。




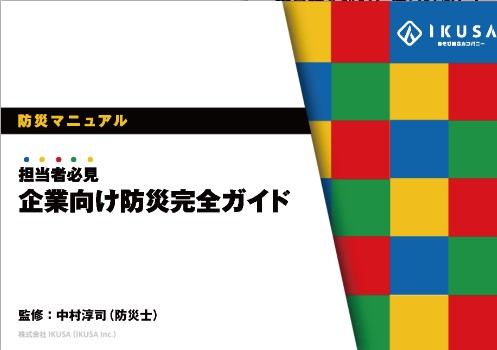





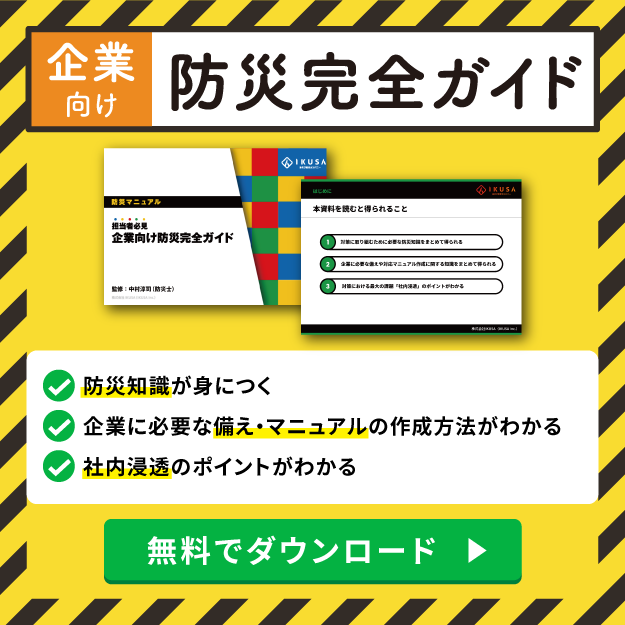


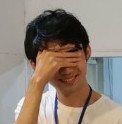 よしふみ
よしふみ
 粕谷麻衣
粕谷麻衣


 チョビベリー
チョビベリー





