
地域における防災活動は、市民の安全を守るうえでも必要な取り組みです。
しかし、防災の経験が浅かったり、これから取り組みをスタートさせたりする際には、どのように取り組めばよいのかがわからないケースが少なくありません。
本記事では、地域の防災に対する取り組み事例を10選ご紹介します。ぜひ今後の取り組みのヒントにしてみてください。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
⇒解説資料のダウンロードはこちらから
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
地域の安全は「防災への取り組み」で守る

地域の安全は、防災への取り組みで守ることが大切です。近年、防災においては自助・共助が注目されています。自分の身を自分で守ると同時に、お互いに助け合えるような地域づくりをするために、地域ぐるみで取り組むことが重要です。
市町村が率先して防災イベントを実施したり、地域の企業や団体を中心に自発的に取り組みを始めたりするなど、最近はさまざまな動きが見られるようになってきました。しかし、まだまだ取り組みが追いついていない地域があることも事実です。
地域によっては「そもそも具体的な取り組みを計画していない」というケースもあります。災害から地域を守るために、前向きに地域の防災への取り組みを推進することが重要です。
地域における防災の取り組みを企画する際のポイント

地域の防災の取り組みを計画する場合、どのようなポイントに沿って考えていけばいいのでしょうか。ここからは、取り組みを考える上でのコツをご紹介します。
実際に体験して防災について学べる取り組みを選ぶ
ただ説明を聞いて防災を学んでいくスタイルではなく、実際に体を動かして体験する形にすることで、災害が発生した際に取るべき具体的な行動をイメージでき、被災時に適切な対応を取りやすくなります。
とくに、避難や救助、給食・給水などは、体験を通して学べる要素が多くあります。体験を通じて具体的に学べる取り組みを計画することが重要です。
被災時に役立つ内容を取り入れる
地域における防災の取り組みに、被災時に役立つ内容を学べる内容を含めることが重要です。たとえば、「避難方法・連絡方法」、「対処方法」といった実践的な内容を学べることで、被災時に役立つ知識が得られます。
地域における防災の取り組み・企画例10選

以下では、地域における防災の取り組み事例について紹介します。
1.防災ワークショップの開催
「防災ワークショップ」は、イベント感覚で楽しめるだけでなく、本格的に防災を学べるのが魅力です。防災グッズや非常食の体験を行うことが一般的です。
非常時の適切な行動に関する知識は、頭で理解しているだけでなく、実際に動いて感覚で理解することでしっかりと身に付けることができます。
子ども向けにはクラフト系のワークショップがおすすめです。IKUSAでは、親子で楽しめるワークショップ「防災ヒーロー入団試験」を提供しています。
実際の災害時でも役に立つ、新聞紙を使った「防災スリッパ作り」や防災リュックの中に必要なものを考える「防災リュック間違い探し」など、小さなお子様でも楽しく防災を学べる種目を行います。
親子で防災を学ぶことで、非常時の備えや行動について、改めて考えるきっかけになるでしょう。
2.消火活動体験
多くの災害で発生する可能性のある火災に対処できるようになることは、防災において重要なポイントの1つです。実際に消火器を使用して消火活動を体験することで、火災が発生した際にも迅速に対処し、初期消火ができる可能性があります。
消火活動体験は、消防署が実施することが一般的です。消防署のなかには、初期消火、応急処置・救命、非常食などを体験できる防災イベントを実施した例もあります。消火活動に限らず、関係する防災知識も得られるように企画することで、地域の防災を促進させることにつながります。
3.防災トランプで自助共助の体験
防災トランプは、ゲームを通じて防災について学べるトランプです。ババ抜きやポーカー、大富豪などのトランプゲームを実施し、カードに記載されている防災に関するお題に沿って会話をすることで、防災について学べる仕掛けが施されています。
遊び方の例
- 神経衰弱:揃わなかった札の話をすると3枚目をめくれる
- ババ抜き:捨て札の話をすると次の人に手札を2枚引いてもらえる
- ポーカー:「防災役」という特別な役を作ることができる
子どもでもわかりやすいゲームであるだけでなく、直感的に遊べることから、地域の防災の取り組みとしておすすめです。
4.オンライン防災イベント
「オンライン防災イベント」とは、オンライン配信、オンラインで行うグループワークなど、オンライン開催の防災イベントです。オンラインで実施することで参加するハードルが下がったり、会場のキャパシティが小さいリアルイベントよりも多くの参加者を募れたりするなどのメリットがあります。
株式会社IKUSAでは、2020年12月に兵庫県西宮市のオンライン防災イベントを開催。ファミリー世帯を中心に、多くの参加者にイベントを楽しんでもらうことができました。
イベントの詳細はこちら▼
事例記事:オンラインで防災を学ぼう!西宮市「おうち防災運動会」開催レポート
オンラインで防災を学ぼう!西宮市「おうち防災運動会」開催レポート
具体的なイベント内容は、リモート環境で楽しむ「おうち防災運動会」です。
防災×運動会がコンセプトのアクティビティで、おうちの中で完結するプログラムが特徴。新型コロナウイルスの感染リスクを回避しつつ、防災について学びながら、体を動かして楽しむことができます。
防災の間違い探しや非常食探索、防災をテーマにした借り物競争など、おうち防災運動会ならではのプログラム設計が魅力です。おうち防災運動会の資料ダウンロードはこちらおうち防災運動会のお問い合わせはこちら
5.避難訓練
避難訓練は、重要度が高い防災活動の定番です。非常時における行動を普段から意識しておくことで災害時に適切な行動をとることができます。
避難訓練を行う際には、沿岸部であれば津波に対応した訓練、山間部であれば土砂災害や噴火に対応した訓練など、地域の地理特性を十分に考慮した上で、避難所や避難経路を設定しましょう。
6.給食・給水訓練
災害が発生すると物流がストップし、近隣のお店では物資が少なくなります。そのため、地域が連携して給食や給水活動を行う必要があります。給食に必要な道具の揃え方から、備蓄品の場所の確認に至るまで、実際に一通りやってみることで被災時の迅速な対応につなげることができます。
7.救出・救助訓練
大きな災害が発生すると、交通に混乱が生じることが予測されるため、消防や救急の対応が遅れてしまうこともあるでしょう。そのような状況に備えて負傷者への対応を学ぶ救助・救出訓練を行うことで、住民同士の助け合いにより生存の可能性が高まります。
例えば地震であれば、建物が倒壊し、脱出困難に陥ることが考えられます。バールやのこぎりなど、身近なもので救助する方法や、応急手当ての仕方を訓練で学んでもらうことが効果的です。
参考:東京消防庁<てびき・ハンドブック><消防少年団 高校生団員のてびき><第10章 救助・救出訓練の指導>
8.ハンドブックの作成・配布
災害時の避難経路や危険箇所、避難所を記載したハンドブックを作成し、住民に普段から防災を意識してもらうことで、災害時に混乱せず適切に避難できるようになるでしょう。避難訓練と同様に、地域が注意すべき災害に応じた危険箇所や注意すべき点を記載することが重要です。
福島県郡山市では「わが家の防災ハンドブック」として災害対策基本法の一部改正に伴う避難情報の変更や災害への日頃からの備え、災害時の注意点、洪水ハザードエリアと避難所などを掲載しています。
9.自主防災組織の育成
災害時には「共助」もとても重要になるため、「人と人との繋がり」を構築しておくことも重要です。共助を実現する「自主防災組織」とは、災害による被害を予防・軽減するために自主的に結成される組織です。
災害時に住民同士が助け合う仕組みを作ることができれば、行政の対応に頼らなくても適切な対応が取れるようになり、被害を軽減することにつながります。
自主防災組織の育成については、消防庁が参考資料を公開しています。
10.情報伝達シミュレーション訓練
被災時には災害の正しい状況や避難状況を知ることがとても重要ですが、機器の故障や電波の混乱により、情報伝達をスムーズに行うことができないことも考えられます。災害時に迅速な対応をするため、非常時の情報伝達手段を確認したり、実際に使用してみるシミュレーション訓練が大切です。
こちらの資料では、「衛星携帯電話」やマルチメディア振興センターの運営する情報基盤「Lアラート」など、非常時に活用することのできる情報伝達手段が紹介されています。
まとめ

地域における防災への取り組みは、地域を守るために必要です。
自然災害での被災は、決して他人事ではありません。自然災害が多い日本に住んでいる限り、誰の身にも降りかかる可能性があります。自助・共助ができる地域を目指していくことが大切です。
ぜひこの記事でご紹介した事例も参考に、防災への取り組みを今一度考えてみてはいかがでしょうか。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/

1993年生まれ。栃木県在住。一児のシングルマザーライター。Web媒体・紙媒体にて、ジャンルを問わず多くのメディアで執筆。BtoB向け記事の他、ママ目線でのコラム執筆も手掛ける。専門家や起業家などへの年間インタビュー数200人を目標に、パワフルに活動中。

「やらないと」から「やってみたい」と思える防災へ。防災を楽しく学べるイベント「あそび防災プロジェクト」の発案者。防災運動会をはじめとした様々なサービスを考案。企業や自治体、商業施設での防災イベントの実施や、「世界防災フォーラム2019」「防災アイディアソン BOSAI Startups in Japan」へ登壇。「あそび防災プロジェクト」は2020年グッドデザイン賞を獲得した。




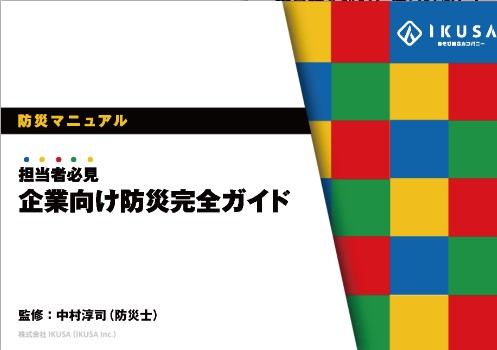





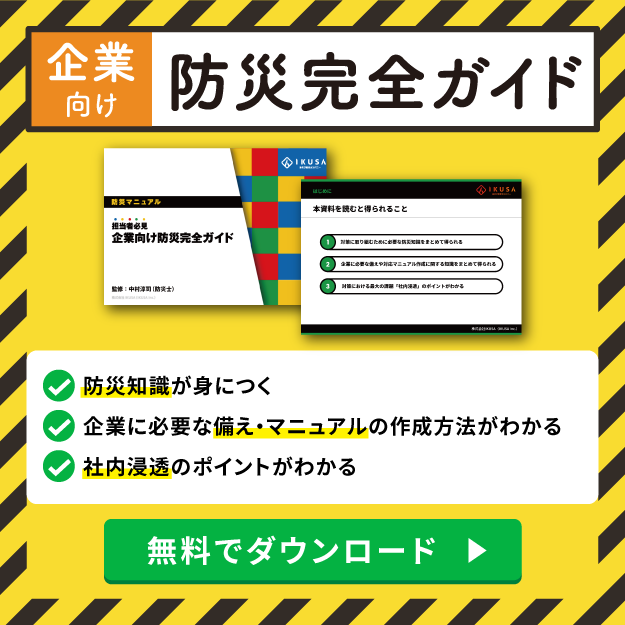


 齋藤遥
齋藤遥

 JJ
JJ
 あそび防災情報局
あそび防災情報局

 粕谷麻衣
粕谷麻衣


