昨今の自然災害は激甚化・頻発化しており、企業でも危機感が高まっています。地球温暖化の影響もあり、洪水や大型台風、地震、土砂崩れ、津波、落雷などが国内のいつ、どこで起きても不思議ではない状況になっているため、事業中断をせざるを得ないケースも見受けられます。いざ緊急事態に陥った場合のことを想定し、知識を深めたり備蓄をしたりと対策を講じることが重要です。では、何から手を付けるべきなのでしょうか。
本記事では、防災と減災の違い、「防災の三助」の概要、防災や減災の取り組み・注意点について、実施されている事例とともに解説します。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
防災と減災、どう違う?

一般的には、災害対策としては「防災」という言葉が使われますが、文字通り災害を防いだり被害をできるだけ「ゼロ」にするために、あらかじめ準備することを意味します。例えば、川の氾濫や津波を想定した「防波堤」・「堤防」を設置することや、地震に備えて社屋を補強することなどです。
一方の「減災」は、「災害による被害をできる限り最小限にすること」。災害が起こることを想定している点で、防災とは違いがあります。
かつては「防災」の考え方が主流でした。しかし、1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災のような大規模な自然災害が実際に起こった際、それまでの防災対策が十分に機能しないことが明白になりました。さらなる巨大地震や大規模な集中豪雨、大型台風などがこの先に起こると考えると、その被害を完全に防ぐことも不可能でしょう。その分、被害が発生することをあらかじめ想定して、より合理的で現実的に被害を抑えるべく「減災」に取り組むことも重要視されるようになったのです。
自然災害大国である日本では、回避できる災害は「防災」し、被害があったとしても「減災」できる体制づくりが必要とされているのです。
重要な「防災の三助」とは
三助とは、次の3つを指します。
- 「自助」=自分と家族の命、財産を自分で守ること
- 「共助」=近隣住民や被災者同士で互いに助け合うこと
- 「公助」=行政による公的な支援のこと
減災の観点からこの3つの連携がスムーズであることが大切だと言われています。
例えば災害発生直後だと、まずは自分と家族で助け合うはずですが、公的な救助活動が開始するまでにはしばらく時間を要します。そのときに、近隣住民や地域での共助活動が重要な意味を持ちます。日頃から防災訓練や地域行事で良好な関係性が築けていれば、いざという時に助け合うことができるでしょう。
企業での防災・減災の取り組み例

近年の大きな災害被害を踏まえ、防災・減災の意識は高まりつつあります。企業で行われている取り組みを紹介します。
危険区域や避難経路の確認
会社や関連設備、従業員の自宅周辺のハザードマップを確認し、どんな災害が起こりやすいか災害リスクを把握します。ハザードマップは定期的に更新されるので、節目ごとに確認することがおすすめです。
防災設備の設置・導入
消火設備や耐震性の有無などは基本的な企業防災として必須なので、確認しておく必要があります。また、オフィス家具や機械を固定して転倒を防いだり、ガラス窓が割れた際の飛散を防ぐフィルムなどを活用することも重要です。
さらに、停電時に活用できるソーラー電源灯や蓄電池、災害対応トイレ、避難先や避難経路が一目でわかる「警告サイン」など、大災害時の避難生活を想定した設備を設置するケースも増えています。
避難経路と安否確認の手順を決める
例えば水害が起きた場合、上層階への移動にするのか、工場や倉庫にある設備はどうするのか、お客さまがいる時間帯ならどのように誘導するのか、などいくつものシチュエーションで考えることがおすすめです。具体的に考えてみることで課題も見えてくるでしょう。
備蓄品の準備
従業員が少なくとも3日、できれば1週間程度過ごせる備蓄品を準備することが推奨されています。水、食糧のほか、毛布や簡易トイレ、マスクなどの衛生用品、乾電池やラジオなどもあるといいでしょう。
避難訓練
小学校や中学校、高校などはもちろんのこと、未就学児たちを含む保育園や幼稚園など、また自治体や企業でも、避難訓練は多く行われています。実際、過去に発生した大災害では、「逃げ遅れた」「災害現場に戻ってしまった」などで失われた命も多く、避難の重要性を知ることは大きな意味をもっています。
特に企業では、従業員の安全を守り、事業を継続させるためのBCMやBCPを策定することが推進されていますが、策定するだけではなく、従業員への教育として緊急時の訓練を行う必要があります。
なお、避難訓練は「シナリオあり」「シナリオなし」の2つのタイプで行うことがおすすめです。あらかじめ災害の種類や従業員の行動をシナリオで決めておきて、十分な対応が可能であるか否かを検証するシナリオありの避難訓練では、各自が自覚をもって役割を果たす練習ができます。シナリオなしの場合は、1人ひとりが自ら考えて行動する必要があります。いずれも、課題が見えてくることが多いため、定期的にシナリオあり・シナリオなしの避難訓練を実施するとよいでしょう。
災害時の体制作り(BCM・BCP)
災害発生時、企業は従業員の安全の確保と、被害を最小限にして事業を継続するための対処を行う必要があります。内閣府からも、その運営方針(BCM)や具体的な行動指針(BCP)をあらかじめ策定しておくことが推進されています。
いろいろと災害を想定して防災・減災に取り組んでいても、実際は複合的に困難な状況が発生し、混乱やパニック状態に陥るものです。あらかじめ、企業の設備や備品の状況、資金面、人の配置や関連企業との連携などを確認しておき、何を優先して行動すべきかを考え、それを従業員にも周知しておく必要があります。
また、可能であれば地域への「共助」として、地域住民のための支援も念頭に置くと言いでしょう。社屋の一部を避難場所にしたり、備蓄を配布したりといったことができれば、地域との繋がりも深まるはずです。
災害ボランティアトレーニング
毎年のように、災害時ボランティアの活動が伝えられるようになりました。災害直後の片づけ作業や被災者支援、地域の復興に役立つ災害ボランティアですが、具体的知識がなければ役に立たなかったり、逆に足手まといになるのではないか、と気おくれする人も多いようです。
実際に被災地ではライフラインや物資が不足していたり、十分に食事や宿が確保できない場合も想定されるうえ、作業自体にも危険が伴うため、服装や持参品にはある程度の知識がある方がいいでしょう。
防災イベント・防災教育
近年ではレクリエーション感覚で防災・減災を学べるような趣向を凝らしたプログラムが増えています。子どもも一緒に参加でき、遊び感覚で知識を身に付けられるので、防災意識を高められるだけでなく、企業として主催すれば地域貢献の一助にもなります。
防災ヒーロー入団試験
防災ヒーロー入団試験は、体を動かしながら防災について考え、学べるイベントです。「事前準備・災害発生・発生直後・避難生活・生活再建」という防災の5つのフェーズに対応した競技を通じて、防災を体験できます。
種目は「防災スリッパづくり」「水消火器射的」「スモーキー迷路」など、親子で楽しめて、実際に役立つ内容になっております。防災教育イベントや、親子での防災訓練におすすめです。
資料をダウンロードする災害都市からの大脱出

災害都市からの大脱出では、周遊型の謎解きゲームを通じて防災を学ぶことができます。謎解きを楽しみながら防災知識を得られ、周遊して街の危険区域や避難場所、施設の避難経路を実際に通って学べることが災害都市からの大脱出の特徴です。
謎解きの難易度は小学生でも楽しめるように調整することができ、商業施設や地域の防災イベントやファミリー参加型の社内イベントなど、カスタマイズして開催するのもおすすめです。
資料をダウンロードする防災フェス
防災フェスは、体験型の防災イベントです。防災知識を楽しく学べるオリジナルアクティビティや、防災のプロによる講演会、非常食体験など、多様な防災コンテンツで防災について1日かけて学ぶことができます。
地域や来場者に合わせた地産地防のイベントを行えるため、商業施設のファミリー向けイベントや、地域・自治体の防災啓発イベントなど、幅広くご活用いただけます。
資料をダウンロードするおうち防災運動会
上記のイベントは対面開催のものですが、リモート開催の需要が増えてきた最近では、オンラインで防災を学べる「おうち防災運動会」もあります。
 こちらはビデオチャットツールを用いた、オンライン完結型の防災イベントです。種目例としては、家にある非常食を探す「おうち探検!非常食捜索トライアル」や家庭の防災に関するVTRを見て間違いを探す「防災間違い探しオンライン」などが挙げられます。自宅にいるからこそ学ぶべき知識や考え方を、楽しみながら習得することができます。子供も一緒に楽しめる防災イベントとして、自治体のイベントや企業のファミリーイベントなどで活用されています。
こちらはビデオチャットツールを用いた、オンライン完結型の防災イベントです。種目例としては、家にある非常食を探す「おうち探検!非常食捜索トライアル」や家庭の防災に関するVTRを見て間違いを探す「防災間違い探しオンライン」などが挙げられます。自宅にいるからこそ学ぶべき知識や考え方を、楽しみながら習得することができます。子供も一緒に楽しめる防災イベントとして、自治体のイベントや企業のファミリーイベントなどで活用されています。
防災・減災における教育は、いざというときに役立つもの。学校や自治体だけではなく、企業も積極的に防災・減災の教育を進めていかなければなりません。

せっかく防災・減災の対策をするのなら、合理的で実効的なものを行いたいもの。地域の特性をはじめ、いくつかの点に注意をすることが必要です。
地域の災害の特性に合わせた取り組みを実施する
まず「地域の災害の特性に合わせた取り組みを実施すること」が大切です。
国土交通省が公表しているハザードマップは確認しましょう。ハザードマップは地震、洪水、土砂災害など、過去の災害データや地理情報をもとに、それぞれの地域で起こる災害を予測し、被害範囲を地図にしたもの。災害の素因となる地形や地盤、避難経路などがマップ上でわかります。
山、海、川など、地形に違いがあれば想定される災害も大きく変わります。また地盤の状態いよっては地震や土砂崩れの可能性もあるかもしれません。普段見ているだけでは感じられない災害リスクが意外と潜んでいるかもしれません。自治体で配布しているだけでなく、PCやスマホでも確認できます。
地域の災害の特性に合わせて、必要な取り組みを実施してください。
時系列ごとに必要な取り組みを考える
災害発生時は、時系列ごとに「事前対策」「被災直後」「被災後の復旧」の3つのフェーズに分けられます。適切な災害対策を実施するためには、時系列ごに取り組みを考えるといいでしょう。
事前対策は日用品の備蓄や設備の補強のほか、バックアップシステムの導入、防災訓練などが挙げられるでしょう。
被災直後は、従業員の安否確認方法や避難方法、指揮系統の明確化などが必要です。
また、被災後の復旧においては、事業の中断が必要か、中断した場合はどの事業を優先的に復旧させるか、どの手順で復旧するか、といった方針を決め手おく必要があります。
災害時に1日でも早く普段通りの日常に近づけるためにも、時系列ごとにイメージをもつことが大事です。また、できる限り「被害規模」も明確にしたうえで、取り組みを検討することがおすすめです。水害や地震など、被害規模は大きく異なるもの。「壊滅的な被害に遭ったら……」「深刻ではあるものの復旧のめどが立ちそうな被害規模だったら…」など、前提となる災害規模をシミュレーションしながら、必要な取り組みを検討してみてください。
「知るだけ」ではなく、実際に行動してみる
防災・減災対策で最も重要といっても過言ではないのが「実際に行動に起こすこと」です。
確かに、防災・減災対策では知ることは大切な要素です。しかし、情報を得ただけでは、いざ災害が発生したときにスムーズに立ち回れるとは言い切れません。とくに、災害の規模が大きい場合は、現場が混乱することが予測されます。そのため、被災した状況を想定して、あらかじめ会社全体で行動する必要があるのです。
とくに、定期的な訓練はいざというときの立ち回りをスムーズにするもの。日ごろから防災意識を高めることにもつながりますので、積極的に「行動」を起こしていきましょう。
まとめ
 今回は、防災・減災対策で何をすべきかを解説しました。いずれ来るといわれる大災害に備えるためにも、さっそく今から防災・減災対策を講じることがおすすめです。 全国でさまざまな対策・取り組みが行われているので、参考にしてみてください。
今回は、防災・減災対策で何をすべきかを解説しました。いずれ来るといわれる大災害に備えるためにも、さっそく今から防災・減災対策を講じることがおすすめです。 全国でさまざまな対策・取り組みが行われているので、参考にしてみてください。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
企業における減災の取り組みについては、こちらの記事もぜひお読みください。
防災と減災の違いとは?企業が実施すべき防災対策をご紹介
防災に役立つ豆知識が得られる記事はこちら!
防災の豆知識!知っておくと役立つ20の知識

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!






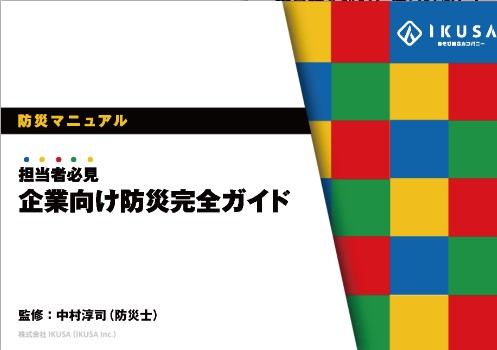





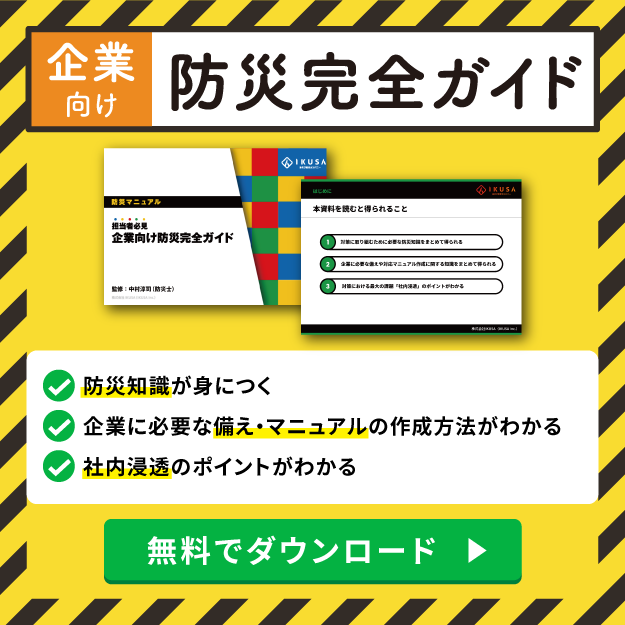


 粕谷麻衣
粕谷麻衣


 JJ
JJ







