地震や水害などの自然災害が多い日本では、防災に対する意識を高め、被害を最小限に食い止める「減災」が重要な課題です。
特に多くの従業員を抱える企業では、災害時に従業員の命を守るためにも、防災対策は欠かせません。
しかし、「具体的にどのような対策が必要なのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、企業で実施できる防災のヒントとして、行政の防災に対する取り組みを解説します。万が一のとき、社員や自分の身を守るためにも、防災対策を強化していきましょう。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
- 目次 -
南海トラフに備えた静岡県の取り組み

いつか起きると言われている南海トラフ巨大地震。ここでは、東海地震の可能性が示唆された昭和54年(1979年)から、40年以上にわたって防災対策に取り組んでいる静岡県の事例を解説します。
津波対策
広く海に面している静岡県では、大津波に備えて平成25年(2013年)に「地震・津波対策アクションプログラム」を策定し、津波対策を強化しています。たとえば浜松市では、住民と協議のうえ、沿岸部に防潮堤を造成中。また掛川市の「ふじのくに森の防潮堤づくり」と呼ばれる活動では、地域に自生する樹木を植樹し、海岸防災林を造成しています。
さらに袋井市には、高潮被害から逃れるための高台として江戸時代に築造された「命山」があります。平成24年(2012年)から28年(2016年)にかけて整備された江戸時代の命山は、現代でも津波被害から逃げるための貴重な一時避難場所です。
このように、沿岸地区に住む住民の合意を得ながら防災に取り組む方式は「静岡方式」と呼ばれています。
防災知識の向上
静岡県では、「ふじのくに防災士」や「ジュニア防災士」など、防災知識に対する資格を作り、個人の防災知識の向上を図っています。
ふじのくに防災士とは、地震・台風・豪雨などの自然災害に関して、専門的かつ実践的な知識を持つ人材に与えられる資格です。静岡県独自の防災総合講座や防災士養成講座を修了し、知事から認定された人がふじのくに防災士を名乗れます。
ジュニア防災士は、地震や風水害などの自然災害から自分の身を守り、家庭の防災リーダーになれる小学校4年生から高校3年生までの人材が対象です。ふじのくにジュニア防災士養成講座を修了し、静岡県にレポートを提出することで、ジュニア防災士の称号を得られます。
このように専門的な防災知識を持つ人材を育成し、防災意識を高めているのが静岡県の特徴です。
インフラの整備
静岡県は、新東名高速道路のすべてのサービスエリアやパーキングエリアに緊急用ヘリポートを設置し、災害時のインフラを整えています。また、内陸部にある新東名高速道路周辺の地域は国の総合特区指定を受け、物流と生産拠点の形成を進行中です。
内陸の中山間地は、津波の被害を受ける可能性が低く、内陸部を開拓する重要なインフラとして位置づけられています。静岡県では、防災と経済の両立を目指し、沿岸部と内陸を結ぶ「内陸フロンティア構想」が推進中です。
人々の生活を支えるインフラは、災害時の物資運搬や避難生活の際にも重要な役割を担うことになります。そのため静岡県では、災害に強いインフラ整備を進めて人々の生活を支えているのです。
東日本大震災の被災地・仙台の取り組み

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県仙台市は、積極的に防災に取り組んでいます。ここでは、仙台市が実施している防災や防災教育についてご紹介しましょう。
都市インフラの整備
仙台市では、地震や津波による都市インフラへの影響を抑えるため、住宅や上下水道の改修工事や耐震工事を実施しています。東日本大震災で発生した津波により破壊された南蒲生浄化センターは、建屋に耐水扉を設置し、巨大津波にも耐えられるように再建されました。
また、震災の影響を受けやすい木造住宅や分譲マンションの耐震化も積極的に実施。たとえば、分譲マンションへの防災活動とマンションの防災力向上を目指し、平成25年(2013年)には「杜の都 防災力向上マンション認定制度」を創設しています。
さらに省エネルギーや再生可能エネルギーの活用を進めながら、持続可能な社会作りに注力しています。
津波に対する多重防御
東日本大震災による津波で大きな被害を受けた沿岸部では、津波被害を最小限にするための取り組みがなされてきました。
たとえば、沿岸に海岸堤防や海岸防災林を整備し、複数の施設で津波を防ぐ「多重防御」。さらに、道路のかさ上げや住居の内陸部への移転といった津波対策を施しています。
津波対策と併せて、避難施設や避難経路の確保も整備しているため、万が一のときでもスムーズな避難が可能です。
防災教育
仙台市では、防災知識を備えた地域のリーダーを養成し、災害時に適切な判断ができるよう児童に対する防災教育を推進。たとえば、災害時の避難経路を確認するために地域の防災マップを作成する活動を実施しています。
また児童が主体的に防災について学べるように、小学校1年生から3年生用、4年生から6年生用、中学生用に3冊の防災教育副読本を用意。震災の体験談や内容で災害時の行動について考えられるような内容となっており、より深く防災について学べる工夫がされています。
また災害時の逃げ遅れを防止するために、避難に支援が必要な人の情報を地域団体に登録する「災害時要援護者情報登録制度」を制定。支援が必要な人は、自ら申告することで登録が可能です。
震災の記憶を発信
東日本大震災でどのような被害があり、何が起こったのかを情報発信することで、今後の教訓にしています。たとえば「せんだい3.11メモリアル交流館」では、震災被害や復旧・復興の状況を展示。震災から復興までの流れを、来館者にわかりやすく伝えています。
また、被災から復興計画期間までの5年間の仙台市の取り組みを記録した「仙台市復興五年記録誌」を発行。震災から得た教訓や防災対策を次世代へ伝える活動を行っています。
このように震災の記録を発信することで、防災に対する意識を高められるでしょう。
防災へのユニークな取り組み

防災への取り組みは、身近なところから実施できます。ここでは、楽しく防災を学べるユニークな取り組みについてご紹介します。
カードゲーム
カードゲームを通じて防災を学べる「クロスロード」は、文部科学省が推進する「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の一環で開発された防災教材です。
カードには、実際の災害現場であった事例がかかれており、その課題に対してYESかNOで自分の判断を示します。参加者同士でそれぞれの判断をシェアして議論することで、災害対応を自分の問題として考えることがこのゲームの目的です。
実際に掲載されているカードの内容には、「人数分用意できない緊急食料をそれでも配るか」や「学校教育の早期再開を犠牲にしても学校用地に仮設住宅を建てるか」などがあります。この内容は、阪神・淡路大震災の際、実際に神戸市職員が迫られた判断です。実際の事例を課題に扱っているため、災害現場のジレンマや苦悩が伝わるでしょう。
災害時の対応には、必ずしも正解はありません。しかし、最善の答えを出すためには、平常時から災害時の対応について誠実に考えることが重要です。このカードゲームを通じて、実際にどのような判断を迫られるのかが事前に学べます。
おうち防災運動会
兵庫県西宮市では、自宅にいながら防災を楽しく学べるオンラインイベント「おうち防災運動会」を実施。おうち防災運動会では、防災を事前準備・災害発生・災害直後・避難生活・生活再建の5つのフェーズに分け、必要な知識や行動を学びます。
オンラインで防災を学ぼう!西宮市「おうち防災運動会」開催レポート
事前準備は、災害前に準備しておきたい備蓄品や避難経路についての内容です。たとえば実際のイベントでは、テーマに沿った非常食を自宅から5つ見つける課題が出されました。課題に合った非常食を自宅で集め、参加者全員でそれぞれの意見を共有することで、非常食への理解を深められます。
災害発生のフェーズは、災害発生時から24時間以内です。自分や家族の命を守るために、適切な行動を行う必要があります。災害直後は、災害発生から72時間以内を指し、健康面や心理面の2次災害が想定されます。おうち防災運動会では、このフェーズを対象に借り物競争を実施。出された課題を自宅にあるものでクリアするのですが、必要な道具が揃っていないことも。その場合、代わりの物を使って課題をクリアしなければならないため、臨機応変に動く力を身につけられます。
避難生活は、災害発生後72時間から3ヵ月です。物資が足りない環境の中で、他の人と協力し合いながら避難所生活を送らなければならないため、思いやりや助け合う姿勢が必要不可欠です。おうち防災運動会では、この点も事前準備のフェーズで併せて学べました。
生活再建のフェーズは、災害発生から3ヵ月以上経過した頃です。避難所生活が終わり日常生活に戻りつつあるなかでも、防災意識を持ち続けることが重要です。
子どもから大人まで防災を楽しく学べるおうち防災運動会は、家族で防災について考えるきっかけになるでしょう。また、社内での防災教育にもおすすめのイベントです。オンラインで参加できるため、会社内で行うのもいいでしょう。
おうち防災運動会の資料ダウンロードはこちらおうち防災運動会のお問い合わせはこちらまとめ

震災や風水害など自然災害の多い日本では、防災は常に意識して取り組むべき重要な課題です。国や各自治体では、被害を最小限に抑える減災や防災など、さまざまな取り組みが実施されています。防災について積極的に学び、災害時の対応を身につけることは、生き残るためにも不可欠だといえるでしょう。
自治体が実施している大掛かりな防災対策はできなくとも、一人ひとりが災害について学び、考えることは難しくありません。企業でも防災に真剣に取り組むことで、災害時に従業員の身を守れます。防災研修にゲームやイベントを取り入れることで、より楽しく学べるでしょう。
防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/

BtoB向けの記事を中心にWeb媒体にて執筆。最近は薬機法を意識した記事の執筆やリライトがメインですが、ライフスタイルや転職関連のジャンルなど幅広く活動中。

「やらないと」から「やってみたい」と思える防災へ。防災を楽しく学べるイベント「あそび防災プロジェクト」の発案者。防災運動会をはじめとした様々なサービスを考案。企業や自治体、商業施設での防災イベントの実施や、「世界防災フォーラム2019」「防災アイディアソン BOSAI Startups in Japan」へ登壇。「あそび防災プロジェクト」は2020年グッドデザイン賞を獲得した。





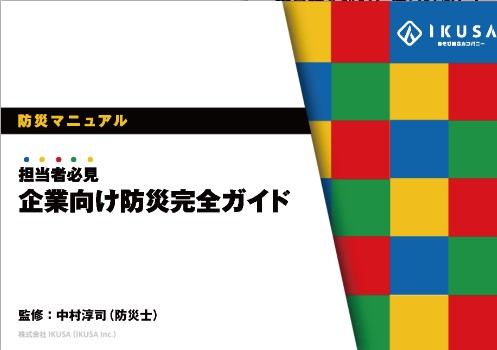





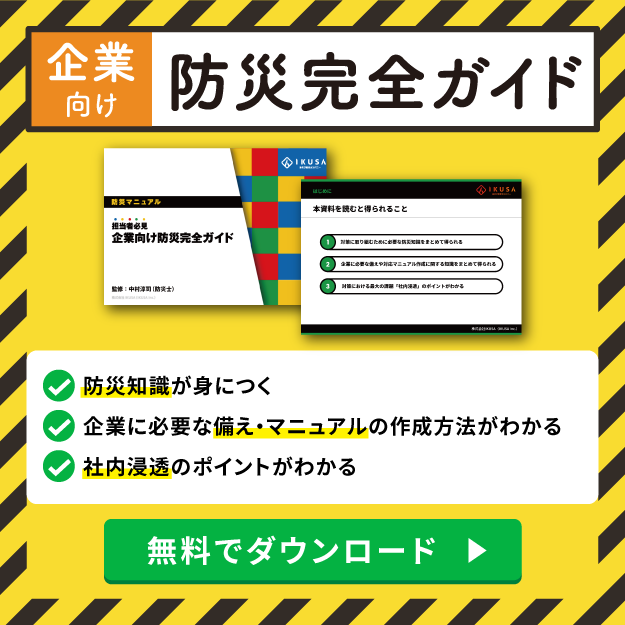


 あそび防災情報局
あそび防災情報局

 粕谷麻衣
粕谷麻衣
 粕谷麻衣
粕谷麻衣






