地震や台風などの災害に備えて、防災グッズを準備しようと考えるとき、多くの人がまず「水」を思い浮かべるでしょう。しかし、実際に備蓄しようとすると、どのくらいの量が必要か、どのような種類がよいのかなど、さまざまな疑問が出てきて不安になるかもしれません。
この記事では、災害に備えて備蓄する水の量についてわかりやすく解説します。さらに、ご家庭に合った備蓄水の種類や選び方のポイント、無理なく続けられる管理のコツまで解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 目次 -
災害時における水の重要性

災害が起こると、水道、電気、ガスといった生活を支えるライフラインが止まってしまうことがあります。特に水が使えなくなると、私たちの健康や命に直接的な影響が出ます。喉の渇きをうるおす飲み水としてはもちろん、料理、トイレ、手洗いや体の清潔を保つための生活用水としても水は欠かせません。
給水車などの公的な支援がすぐに届くとは限らないため、支援が届くまでの数日間を乗り切るためにも、各家庭での水の備蓄が非常に大切になっています。
【早見表】防災備蓄の水、必要な「量」と「日数」は?

災害に備えて水を用意する際、「どれくらい必要なのか」は多くの人が抱く疑問です。ここでは飲料水と生活用水に分けて、必要な量と日数の目安を紹介します。
| 家族人数 | 飲料水(1人1日3立) 最低3日分 | 飲料水(1人1日3L) 推奨1週間分 | 生活用水(1人1日10L) 最低3日分 | 生活用水(1人1日10L) 推奨1週間分 |
| 1人 | 9L(約2L×5本) | 21L(約2L×11本) | 30L | 70L |
| 2人 | 18L(約2L×9本) | 42L(約2L×21本) | 60L | 140L |
| 3人 | 27L(約2L×14本) | 63L(約2L×32本) | 90L | 210L |
| 4人 | 36L(約2L×18本) | 84L(約2L×42本) | 120L | 280L |
「飲料水」は1人1日3L × 最低3日分(推奨1週間)
飲料水は「1人あたり1日3L」を目安に準備しましょう。これは、農林水産省などが推奨している基準です。飲み水だけでなく、調理に使う分も含まれています。
備蓄する日数は、最低でも3日分が必須です。災害直後の72時間は人命救助が優先されるため、支援物資が本格的に届き始めるまでには3日程度かかると想定されています。
しかし、東日本大震災のような大規模災害であれば、ライフラインの復旧や支援の到着が大幅に遅れることもあるため、可能であれば1週間分の備蓄があると安心です。
| 家族の人数 | 最低3日分 | 推奨1週間分 |
| 1人 | 9L | 21L |
| 2人 | 18L | 42L |
| 3人 | 27L | 63L |
| 4人 | 36L | 84L |
「生活用水」は1人1日10~20Lが目安
飲料水とあわせて重要なのが、生活用水です。生活用水は、トイレを流したり、手や顔を洗ったり、食器を洗浄したりするのに使用します。
災害時には、衛生環境が悪化しやすく、感染症のリスクが高まります。身の回りの清潔を保つために、生活用水は欠かせません。
必要量の目安は、「1人1日10〜20L」とも言われています。すべてをペットボトルで備蓄するのは現実的ではないため、日頃からお風呂の残り湯をすぐに捨てずに貯めておくことがおすすめです。一般的な浴槽には約180〜200Lの水を貯められるため、トイレの排水や清掃などに数日間活用でき、非常に大きな助けとなります。
【注意】ペット用の水は「飲料水」として別途準備を
犬や猫など、ペットがいる家庭では、人間の備蓄水とは別に「ペット用の水」も備えておきましょう。 環境省のガイドラインでは、ペット用の備蓄として「最低でも5日分」の水とフードを用意することが推奨されています。必要な水の量は、ペットの体の大きさや健康状態によって異なるため、普段どれくらい飲んでいるかを確認し、余裕を持って備蓄しておくと安心です。
備蓄用の水はどれを選ぶ?主な選択肢4つ

備蓄する水には、いくつかの種類があります。代表的な種類である長期保存水とミネラルウォーター、水道水の汲み置き、ウォーターサーバーについて、特徴やおすすめの人を以下にまとめました。
| 種類 | 特徴 | おすすめの人 |
| 長期保存水 | 災害時の備蓄を目的に製造された水。容器が丈夫で蒸発しにくく、5〜15年ほど長期間保存できる。 | 管理を楽にしたい人/こまめな入れ替えが苦手な人 |
| ミネラルウォーター | スーパーなどで購入でき、賞味期限は1〜2年。普段使いしながら飲み切り・補充を繰り返すことで備蓄を維持できる。 | 日常的にミネラルウォーターを飲む習慣がある人 |
| 水道水の汲み置き | 家庭の水道水を清潔な容器にためて備蓄する方法。保存期間は夏で約4日、冬で約10日程度。 | 費用を抑えたい人/こまめに入れ替えができる人 |
| ウォーターサーバー | 定期的にボトルが届くため、自然にローリングストックが実践できる。手動式なら停電時も使用可能。 | サーバーを利用している人/サーバーの利用を検討している人 |
ここからは、それぞれの特徴やメリット、注意点、どんな人におすすめなのかを解説していきます。
長期保存水
長期保存水は、災害に備えることを目的として製造された水です。一般的なペットボトル飲料よりも丈夫な容器を使い、中の水が蒸発しにくいよう工夫されているため、5年、10年、なかには15年といった長期間の保存が可能な商品もあります。
一度購入すれば長期間、交換の手間がかからない点が大きなメリットです。管理が非常に楽なので、備えたいけれど、こまめな管理は避けたいという人に最適です。
ただし、一般的な水よりも価格が少し高めに設定されていることが多いです。手間や費用のバランスを考えて、自分に合った備蓄方法を検討しましょう。
ミネラルウォーター
スーパーやコンビニで普段から購入している、ペットボトルの水を備蓄に使う方法です。賞味期限は製造から1〜2年程度となっています。
ミネラルウォーターを備蓄するメリットは、日常生活と兼用できる点です。普段から飲み慣れた味の水を備蓄でき、賞味期限が近づいても、飲んでしまえば無駄になりません。
賞味期限が比較的短いため、定期的な入れ替えが必要です。日常的にミネラルウォーターを飲む習慣がある人や、管理の手間を惜しまず、無駄なく備蓄したい人におすすめです。
水道水の汲み置き
家庭の水道水を清潔なボトルやポリタンクに汲んで保管する方法です。日本の水道水は塩素で消毒されているため、一定期間であれば安全に保管できます。
ほとんど費用をかけずに備蓄できる点が大きなメリットですが、保存できる期間が短い点に注意が必要です。直射日光の当たらない涼しい場所で保管した場合でも、保存期間の目安は夏で約4日、冬で約10日です。
保存期間を過ぎた水は、洗濯や掃除などの生活用水として使い、定期的に入れ替えましょう。なお、保存した水を飲料用として利用する場合は、必ず煮沸してから使用してください。
ウォーターサーバー
普段からウォーターサーバーを利用している場合、その水を備蓄として活用するのもひとつの手です。定期的にボトルが配送されるため、後述するローリングストックを自然に実践できます。
注意したいのは、サーバー本体が停電時にも使えるかどうかです。電動式ボタン式のウォーターサーバーは、停電すると水が出せなくなる場合があります。ウォーターサーバーの購入を検討している場合は、停電時でも手動で水が出せるコック(蛇口)が付いているタイプや、ボトルから直接水を注げるタイプがおすすめです。
備蓄用の飲料水を選ぶ際のポイント

備蓄用の飲料水を購入しようと決めたとき、次に多くの人が迷うのが「どんな水を選べばよいのか」でしょう。ここでは、水を選ぶ際に確認しておきたい3つのポイントを紹介します。
保存期間
まず確認したいのは、保存期間です。水の種類によって保存期間は大きく異なります。
| 保存期間 | メリット | デメリット | |
| 長期保存水 | 5~15年 | 一度買えば長期間入れ替えが不要で、管理が圧倒的に楽なこと | 一般的な水より価格が割高である |
| 通常の水 | 1~2年 | 価格が安く、普段から飲み慣れたものを選べる | 保存期間が短いため、定期的な入れ替えが必要 |
管理の手間を最小限にしたいなら長期保存水、費用を抑えて日常でも消費したいなら通常の水、というように、ご自身の管理スタイルに合わせて選びましょう。
ペットボトルのサイズ
ペットボトルのサイズも重要なポイントです。一般的には2Lと500mlの2種類がありますが、それぞれにメリットがあります。
2Lボトルは大容量で、1本あたりの価格が安く、備蓄スペースを効率的に使えるのがメリットです。主に自宅での避難生活での調理や飲料水として重宝します。
一方、500mlボトルは持ち運びしやすいサイズで、避難所へ移動する際や給水所へ水をもらいに行く際にも、リュックに入れて持ち出しやすいです。一度開封しても飲み切りやすいため、衛生的というメリットもあります。
どちらか一方だけを備蓄するのではなく、自宅用には2Lボトル、持ち出し用には500mlボトルというように、組み合わせて備えるのがおすすめです。
味や硬度
水は、含まれるミネラル成分の量によって軟水と硬水に分けられます。水1Lあたりに含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分の量を硬度と呼び、この数値が低いと軟水、高いと硬水と分類されます。
日本の水道水や国産のミネラルウォーターの多くは軟水で、口当たりがさっぱりとしており飲みやすいのが特徴です。一方、海外産の水には硬水が多く、ミネラル分が豊富な反面、人によっては飲みにくく感じることもあります。
災害時のように不安を感じやすい状況では、普段から飲み慣れた軟水を選ぶことがおすすめです。特に、赤ちゃんのミルク作りやペット用の水としては、ミネラル分の多い硬水は体に負担をかける可能性があるため、軟水を選びましょう。
備蓄用の飲料水の管理には「ローリングストック」がおすすめ

備蓄用の飲料水の管理でよくある失敗は、気づいたら賞味期限が切れていたということです。この問題を解決するのにおすすめなのが「ローリングストック」による管理です。
ローリングストックとは、備蓄(ストック)を、日常的に回転(ローリング)させる管理方法です。具体的には、普段から水や食料を少し多めに買っておき、賞味期限が近いものから順番に日常で消費し、消費した分だけ新しく買い足していきます。これにより、常に新しい備蓄を一定量保つことができます。
ローリングストックのメリット
ローリングストックには、以下のようなメリットがあります。
- 賞味期限切れを防げる
- 管理が楽で経済的
最大のメリットは、備蓄品を無駄にしなくて済むことです。「防災用」としまい込むと、存在を忘れてしまいがちですが、日常的に消費することで賞味期限が切れる前に使い切ることができます。
さらに、高価な長期保存水を購入しなくても、普段から利用しているミネラルウォーターで手軽に備蓄を始めることが可能です。管理の負担を軽減し、経済的にも無理なく続けられる方法です。
ローリングストックのデメリット
非常に便利なローリングストックですが、以下のようなデメリットもあります。
- 家族でルールを共有する必要がある
- 備蓄スペースが余分に必要
「古いものから使い、使った分を買い足す」というルールを守る必要があり、ある程度の管理意識が求められます。「気づいたら全部飲んでしまっていた」という事態を防ぐために、家族でのルール共有が必要です。
また、普段使う分に加えて備蓄分を保管するスペースも確保する必要があるため、キッチンの収納やパントリーなど、通常よりも広い保管スペースが必要になります。
家族で無理なく続けるコツ
ローリングストックを無理なく続けるには、仕組み化と習慣化がポイントです。「毎月1日は備蓄確認の日」と決めたり、「水は必ず2箱買い、1箱目がなくなったら新しい1箱を注文する」というルールを決めたりしましょう。また、家族全員が迷わないように、保管場所に「備蓄用(先に使わない)」「日常用(ここから使う)」とラベリングするのも効果的です。
最初から完璧を目指さず、ご家庭のペースで始めてみましょう。
備蓄用の飲料水は分散して保管しよう

備蓄用の水を「どこに置くか」は、意外と見落とされがちな大切なポイントです。
一か所にまとめて置くのではなく、複数の場所に分けて置く「分散保管」をおすすめします。もし備蓄場所をクローゼットの奥など1箇所にまとめていた場合、地震で家具が倒れて取り出せなくなったり、その部屋が浸水被害に遭ったりすると、せっかく備えた水がすべて使えなくなるからです。
分散保管は、そのようなリスクを減らすための賢い方法です。すぐに取り出せる場所と備蓄する場所に分けて保管しましょう。水の保管におすすめの保管場所は、以下の通りです。
- キッチンやパントリー:日常のローリングストック用
- 玄関や納戸:持ち出し用リュックの近く
- 寝室:就寝中の被災に備えて
- 車の中:移動中や車中泊に備えて
一方で、水の保管に向いていない場所もあります。水は直射日光と高温多湿に弱く、品質が劣化しやすいため、ベランダや窓際、夏場に高温になる屋根裏などは避けましょう。また、防虫剤や芳香剤、灯油など、臭いの強いものの近くに置くと、水に臭いが移ってしまう可能性がある点にも注意が必要です。
水と一緒に備えておきたい防災グッズ

災害時に備えて用意すべきものは、水だけではありません。水道・電気・ガスなどライフラインが止まった状況を想像し、これがないと困ると思うものを優先的に準備しましょう。ここでは、水とあわせて備えておきたい防災グッズを紹介します。
| カテゴリー | 主な備蓄品 | 補足 |
| 食料品 | アルファ米/缶詰/レトルト食品/カップ麺/栄養補助食品/お菓子 | 電気やガスが使えなくても食べられるものを選ぶ |
トイレ用品 | 携帯トイレ/非常用トイレ/トイレットペーパー/消臭スプレー/ゴミ袋 | 家族の人数×3〜7日分を目安に用意する |
衛生用品 | ウェットティッシュ/体拭きシート/ドライシャンプー/歯磨きシート/マスク/消毒用アルコール/常備薬・生理用品・おむつ | 特にウェットティッシュは多めに備蓄を |
情報収集ツール | 携帯ラジオ/モバイルバッテリー/乾電池 | 停電時の情報源としてラジオが有効 |
停電対策グッズ | 懐中電灯/ヘッドライト/ランタン/予備電池 | 各部屋に1つずつ分散保管。夜間の安全確保に欠かせません。 |
寒さ対策グッズ | 使い捨てカイロ/アルミシート/毛布・寝袋/防寒着 | 冬場の停電に備え、体温を逃がさない工夫を。アルミシートは軽くて効果的。 |
食料品
水と同様に命を左右するのが食料品です。電気やガスが使えなくても、食べられるものを用意しましょう。
- アルファ米:水やお湯で戻せるご飯
- 缶詰:おかず、果物など
- レトルト食品:カレー、おかゆなど
- カップ麺
- 栄養補助食品:カロリーメイト、ゼリー飲料など
- お菓子:チョコレート、飴など
食料品も水と同様に、ローリングストックで管理するのがおすすめです。
トイレ
水が使えなくなると、水洗トイレは流せなくなります。そのような状況でも用を足せるように、携帯トイレや非常用トイレを用意しておきましょう。
- 携帯トイレ:凝固剤と処理袋がセットになったもの
- 非常用トイレ:便器にかぶせて使うタイプ
- トイレットペーパー:多めに備蓄
- 消臭スプレーや大きめのゴミ袋:臭い対策として
特にマンションなどでは深刻な問題になりやすいため、最低3日分、できれば1週間分を目安に備蓄してください。
衛生用品
水が使えない状況では、衛生環境は一気に悪化します。感染症を予防するためにも、以下の衛生用品が必要です。
- ウェットティッシュ
- からだふきシート
- ドライシャンプー
- 歯磨きシート
- マスク
- 消毒用アルコール
- 常備薬・生理用品・おむつ(必要な方)
衛生用品は体調管理とストレス軽減に直結します。特にウェットティッシュは手洗いや清掃などさまざまな場面で使えるため、多めに用意しましょう。
情報収集ツール
災害時は状況の変化が早く、誤った情報に惑わされると、命に関わるおそれがあります。そのため、正しい情報を得ることが非常に重要です。
しかし、停電するとテレビが見られず、スマホの充電も切れてしまうことがあります。そのような事態に備えて、以下のツールを準備しておきましょう。
- 携帯ラジオ:乾電池式、または手回し充電式
- モバイルバッテリー:大容量のもの
- 乾電池:ラジオやライト用に多めに
モバイルバッテリーの充電切れを防ぐため、定期的に充電状態を確認しておきましょう。
停電対策グッズ
停電は、照明の確保だけでなく、夜間の安全や寒さ・暑さへの対策に直結します。特に災害時は停電が長引くこともあるため、暗闇でも安全に行動できる明かりの確保が欠かせません。スマホのライトは電池消費が激しいため、以下のような専用のライトを準備しましょう。
- 懐中電灯
- ヘッドライト
- ランタン
- 予備の乾電池
- ライト類は、すぐに手に取れる場所に置いておくのが大切です。寝室やリビングなど、複数の部屋に分散して置いておきましょう。
寒さ対策グッズ
冬場の停電では、暖房器具が使えなくなり、低体温症など命に関わる危険につながることがあります。電気を使わずに体を温められるアイテムを備えておきましょう。
- 使い捨てカイロ
- アルミシート
- 毛布・寝袋・厚手の靴下や防寒着
アルミシートは非常に薄く軽量ですが、体に巻くだけで体温を逃がさず、効果的に保温できます。防災リュックにも入れておきたい必需品です。
水の備蓄に関するよくある質問

最後に、災害に備えた水の備蓄に関するよくある質問をご紹介します。
備蓄水の賞味期限が切れてしまったら?
すぐに捨てる必要はありませんが、飲むのは避けましょう。ペットボトルの水は適切に密閉・殺菌処理がされているため、未開封で冷暗所に保管されていれば、賞味期限が切れてもすぐに腐りにくくなっています。ただし、メーカーが保証する風味や品質は低下しており、容器のわずかな隙間から雑菌が入る可能性もゼロではありません。
賞味期限が切れた水は、生活用水として有効に活用しましょう。トイレを流したり、洗濯や掃除に使ったりするなど、さまざまな使い方があります。
生活用水として、お風呂の残り湯はどんなことに使えますか?
災害時に水が使えなくなると、トイレも流せなくなります。その際、お風呂の残り湯をバケツで汲み、便器に流し込めば、排水管に排泄物を流すことが可能です。
また、衛生面に注意すれば、手洗いや洗濯にも活用できます。
赤ちゃんやペット用の水は、大人の備蓄水と同じで大丈夫?
軟水であれば、基本的に大人用と同じで問題ありません。赤ちゃんは内臓がまだ発達途中のため、ミネラル分が多い硬水でミルクを作ると、下痢などを起こす可能性があります。ペットも同様に、硬水が尿路結石などの原因になる場合がありす。
そのため、大人が飲むために硬水を備蓄しているご家庭では、赤ちゃんやペットのために別途軟水を用意しましょう。
まとめ

この記事では、災害への備えとして特に重要な水の備蓄について、必要な量や管理方法までを解説しました。備蓄のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 飲料水は1人1日3立、日数は最低3日分(できれば1週間)
- トイレなどに使う「生活用水」も忘れずに用意する
- ローリングストックでの管理なら、賞味期限切れを防ぎ、無駄なく備蓄できる
- 保管は分散保管で、取り出せなくなるリスクを避ける
災害はいつ起こるかわかりませんが、準備を始めるのに早すぎるはありません。「まだ準備していない」という方も、この記事を読んだ今日が、あなたの家庭防災を始める絶好の機会です。
まずは、ご家族の人数分×3日分の飲料水を用意することから始めましょう。その第一歩が、いざという時にあなたと大切な家族を守ることにつながります。
また、水以外にも食料品や衛生用品、停電対策グッズなど、災害時に必要なものは多岐にわたります。すべてを一度に揃えようとせず、必要なものから少しずつ備えていくことが長く続けるコツです。無理のないペースで家庭の防災を進めていきましょう。

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!



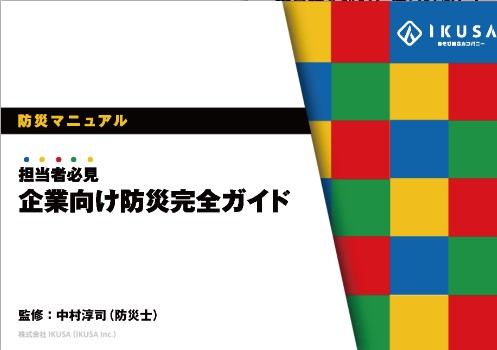





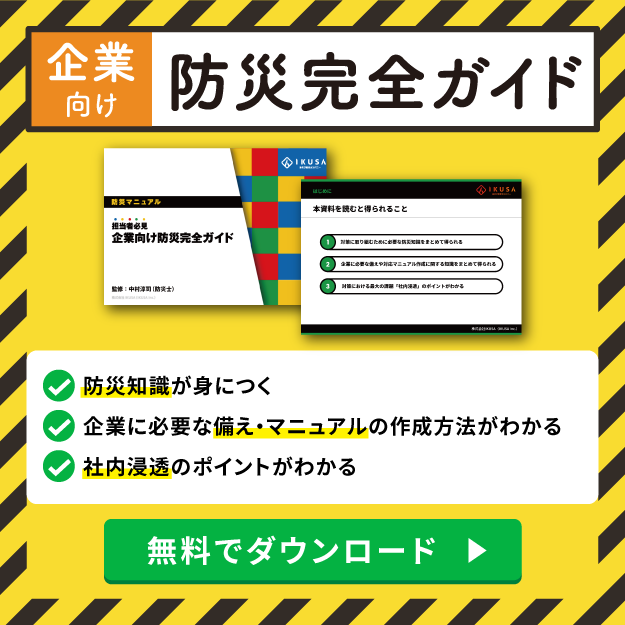


 粕谷麻衣
粕谷麻衣




 あるぱか
あるぱか



