「離れて暮らす高齢の親を、災害から守りたい」「自分たちの体力で安全に避難できるか不安」と考えたとき、まず思い浮かぶのが「防災グッズの準備」ではないでしょうか。とはいえ、いざ準備するとなると「一般的な防災セットで本当に十分なのだろうか」「高齢者には、どのような備えが必要なのか」といった、多くの疑問が出てくるでしょう。
本記事では、高齢者に特別な配慮をした防災グッズが必要な理由を説明します。さらに具体的な防災グッズから、後悔しないための選び方のポイント、グッズ以外の重要な準備まで解説するので、参考にしてください。
- 目次 -
なぜ高齢者には「特別な配慮」をした防災グッズが必要なのか?

高齢者の防災について考える際、「普通の防災セットでも大丈夫なのでは?」と思われるかもしれません。しかし、高齢者には若い世代とは異なる事情があり、特別な配慮が不可欠です。
ここでは、その主な理由を3つご紹介します。
理由1:体力の低下と身体機能の変化
高齢になると、筋力や持久力が落ちるだけではなく、バランス感覚や視力・聴力も衰えていきます。わずかな段差や暗い場所でも転倒の危険が高まり、重い荷物を背負ったり、複雑な操作が必要な道具を扱ったりすることが難しくなります。
そうした身体的な変化を踏まえると、一般的な防災セットでは十分に使いこなせない可能性があります。高齢者でも無理なく持ち運び・使用できるように、「軽くてシンプルな防災グッズ」や「片手でもすぐに使える設計」のものを選ぶことが欠かせません。
理由2:持病や常備薬への依存
高血圧や糖尿病といった持病がある方にとって、薬は命をつなぐものです。しかし災害時には、物流が止まり、医療機関も被災して薬が手に入らなくなることがあります。実際に、薬が手に入らないことで持病が悪化し命を落とす「災害関連死」は、避難時における大きな問題です。
そのため、高齢者には「常備薬をまとめて保管できるケース」や「お薬手帳を入れて持ち歩けるポーチ」など、体調管理を支える特別な備えが必要になります。
理由3:情報収集や判断の遅れ
災害時の避難指示などの情報は主にスマホで確認しますが、操作が難しいと感じる高齢者も少なくありません。真偽のわからない情報に惑わされると、逃げ遅れに直結します。
そこで、「操作が簡単なラジオ」や、「必要な連絡先が一目でわかるカード」など、直感的に使えるアイテムを備えることが安全につながります。
これだけは揃えたい!高齢者のための防災グッズ

ここでは、高齢者の方が備えておくべき防災グッズを、「一次持ち出し品」「二次持ち出し・備蓄品」「便利グッズ」の3つのカテゴリーに分けて具体的にご紹介します。
まずは、本記事で紹介するアイテムと、それぞれが高齢者の防災に必要な理由を一覧で確認しましょう。
| アイテム名 | 高齢者の防災に必要な理由 |
| 長期保存水 | 脱水症状を防ぐ。重すぎない500mlがおすすめ。 |
| 栄養補助食品 | 調理不要ですぐにエネルギーを補給できる。低血糖防止や体力維持に。 |
| 手回し充電ラジオライト | 停電時の情報収集と安全確保につながる。電池不要で安心。 |
| モバイルバッテリー | 家族との連絡手段(スマホ)を確保するために不可欠。 |
| 口腔ケアシート | 水がなくても口腔内を清潔に保ち、誤嚥性肺炎を防ぐ。 |
| からだ拭きシート | 入浴できない際の衛生維持と感染症予防、気分転換に。 |
| 簡易トイレ・凝固剤 | 劣悪なトイレ環境を避け、体調悪化や感染症を防ぐ。 |
| 救急セット | 軽度の怪我に即座に対応し、悪化や感染を防ぐ。 |
| ホイッスル(笛) | 少ない体力で助けを呼べる。生存率を高めるお守り。 |
| 軍手・革手袋 | ガラス片や瓦礫などから手を守り、安全な避難を助ける。 |
| 医薬品 | 命に直結する常備薬の確保。災害時は入手困難になる。 |
| 貴重品 | 身元の証明や、災害後の手続きに必要。 |
| 非常食セット | 在宅避難時の食糧を確保する。食べ慣れた味が安心感を得られておすすめ。 |
| 長期保存水(備蓄用) | 飲料水・生活用水として最低3日分以上を確保する。 |
| カセットコンロ | 温かい食事で体力を維持し、精神的な安らぎを得る。 |
| アルミブランケット等 | 避難所の床冷えから体を守り、低体温症を防ぐ。 |
| 大人用紙おむつ等 | 介護に必須。避難所では入手困難なため備蓄が重要。 |
| 使い捨て手袋・マスク | 感染症対策や衛生的な介護のために必須のアイテム。 |
| 折りたたみ杖 | 悪路での転倒を防ぎ、安全な歩行をサポートする。 |
| 携帯用クッション | 硬い床の体への負担を軽減し、体力の消耗を防ぐ。 |
| 入れ歯洗浄剤・専用ケース | 食事ができなくなる事態を防ぎ、健康を維持する。 |
| 緊急連絡先カード | 連絡先を正確に伝え、迅速で適切な救助につなげる。 |
【基本の備え】全員に必要な一次持ち出し品
災害発生時に最初に持ち出すべき最低限のアイテムをご紹介します。リュックにまとめて、玄関や寝室などすぐに手に取れる場所に置いておきましょう。
長期保存水(500ml)
水は生命維持に欠かせない基本的な備えです。高齢者は特に脱水症状になりやすく、脱水は血栓を作り、脳梗塞や心筋梗塞など命に直結するリスクを高めます。また、持病の薬を飲むためにも、飲み水は必要です。
重すぎず持ち運びやすい500mlのペットボトルを1〜2本は、リュックに備えておきましょう。
栄養補助食品・非常食(ゼリー飲料、ようかん等)
災害時は強いストレスで食欲が落ち、固形物が喉を通らない、といった事態は頻繁に起こります。そんな時でも、ゼリー飲料や食べ慣れた甘いようかんなどは口にしやすく、消耗した体力を支えるエネルギー源となります。
特に持病のある方にとっては、低血糖を防ぎ、体調を維持するための欠かせない備えです。火や水を使わず、すぐに食べられるものを選びましょう。
手回し充電ラジオライト
真偽不明の情報が飛び交い混乱する中で、正しい避難情報や支援情報を得ることは、生死を分けると言っても過言ではありません。スマホの操作に慣れていない方でも、スイッチを入れるだけで使えるラジオであれば、正確な情報をすぐに入手できます。
また、停電した夜間の避難所や自宅でトイレに立つ際、物につまずいて転倒するリスクがあります。暗闇での転倒は骨折などの大怪我につながりかねないため、電池切れの心配がない手回し充電式で、足元を照らすライト付きのラジオがおすすめです。
モバイルバッテリー
スマホが充電切れになると、家族との連絡や情報収集ができなくなり、深刻な孤立と不安に陥ってしまいます。避難所の充電ステーションは長蛇の列になることも多く、必ずしも利用できるとは限りません。
自分専用のバッテリーを1つ持っておくだけで、すぐにスマホを充電できます。いざという時の連絡手段と情報源を確保するためにも、モバイルバッテリーをリュックに入れておきましょう。 口腔ケアシート
水が不足して歯磨きができない状況では、口の中の細菌が急激に増殖します。これが唾液などと一緒に気管に入りこむと、災害関連死の大きな要因である「誤嚥性肺炎」につながる可能性が高くなります。
指に巻いて拭うだけで口腔内を清潔に保てる口腔ケアシートは、衛生用品というよりも、命を守るための重要な医療関連アイテムと考えてください。
からだ拭きシート
入浴できない状況が続くと、不快に思うだけでなく、皮膚のバリア機能も低下します。特に高齢者は皮膚が弱いため、あせもや湿疹といった肌トラブルから細菌が入り込み、深刻な感染症を引き起こす恐れがあります。
健康を維持し、尊厳を守るためにも、すぐに体を清潔にできるからだ拭きシートを用意しましょう。
簡易トイレ・凝固剤
不衛生なトイレ環境を避けようと水分や食事を控えてしまうと、脱水症状やエコノミークラス症候群、栄養失調といった二次的な健康被害につながります。また、排泄を我慢することで、膀胱炎や持病の便秘の悪化を招くことも。
衛生的で安心して使える自分専用のトイレは、健康被害のリスクを減らし、尊厳を守るための必需品です。 救急セット(絆創膏、消毒液など)
避難時には、割れたガラス片や瓦礫で手足を切ったり、転倒して擦り傷を負ったりすることがよくあります。高齢者の方は皮膚が薄く、小さな傷でも化膿しやすいため、迅速に処理することが求められます。特に糖尿病などの持病がある場合は重症化しやすいため、自分で応急処置ができるセットを必ず備えてください。
ホイッスル(笛)
地震で家具の下敷きになったり、ドアが歪んで部屋に閉じ込められたりした場合、声だけで助けを呼ぶのは限界があります。声が枯れるほか、煙を吸い込んで声が出せない状況も考えられるでしょう。
ホイッスルなら、少ない体力で、自分の居場所を瓦礫の向こうまで知らせることが可能です。命をつなぐお守りとして、必ず携帯しましょう。
軍手・革手袋
避難時に手をついた先がガラスの破片だらけだったり、素手で熱くなったドアノブに触れてしまったりするかもしれません。手を負傷すると、その後の避難生活であらゆる行動が困難になります。軍手・革手袋などの丈夫な手袋は、障害物を安全にどかしながら避難するための重要な防具です。
医薬品
災害時には、交通網の遮断や医療機関の被災で、日常的に服用している薬が手に入らなくなる可能性が高いです。薬が数日切れるだけで命に関わる事態に陥ることもあるため、必ず数日分を持ち出し用に準備しましょう。
また、避難所にいる医師は、あなたの普段の健康状態を知りません。初対面の医師に正確な情報を伝えるために、お薬手帳も入れておきましょう。
貴重品
身分証明のコピーは、災害後の生活を取り戻すための出発点となる大切な備えです。被災後の生活再建では、あらゆる場面で身分証明が求められます。公的な支援金の申請、保険金の請求、銀行での預金引き出し、仮設住宅への入居手続きなど、身分証明がなければ手続きを進められません。
【避難生活に備える】二次持ち出し・備蓄品
自宅で避難生活を送る場合や、避難所生活が長引く場合に備えて、自宅に蓄えておくことが重要です。ライフラインの復旧には、1週間以上かかることも少なくありません。購入するだけではなく、すぐに使える状態にして置いておきましょう。
非常食セット(やわらかいごはん、おかず等)
災害時に強いストレスがかかると、食欲や消化機能が低下することがあります。そんな時に乾パンや冷たい缶詰だけではなかなか喉を通らず、体力を維持できません。温めるだけで食べられるお粥や、魚の煮付け、野菜の煮物といった、食べ慣れた味のやわらかい食事は、弱った胃腸でも受け入れやすく、何より心を落ち着かせてくれます。気力を保ち、困難な状況を乗り超えるための大切なエネルギー源です。
長期保存水(2L×6本など)
自宅で備蓄する水は、以下のようなさまざまな用途で消費されます。
- 飲料水
- 調理用
- 衛生用(手や顔を洗う)
- 服薬用
特に高齢者は、脱水になるリスクが高い上に、薬を飲むためにも清潔な水が欠かせません。給水車には長蛇の列ができ、重いポリタンクを運ぶのには大きな負担がかかります。自宅に十分な水を備蓄しておくことが、健康維持と負担軽減につながります。
カセットコンロ・ガスボンベ
ライフラインが止まった避難生活において、温かい食べ物が口にできるかどうかは、体と心の健康を大きく左右します。冷たく固い食事ばかりでは、体は冷え、気分も落ちてしまうでしょう。カセットコンロが1台あれば、レトルト食品を温めたり、お湯を沸かして温かいお茶やスープを用意したりすることが可能です。
湯気のある食事は、体温を高め、日常に近い感覚を取り戻させてくれます。ボンベは1週間で1人6本程度必要となります。家族の人数から必要な本数を算出して用意しましょう。
アルミブランケット・エアーマット
アルミブランケットとエアーマットは、体力の消耗や低体温症を防ぐための重要な健康管理アイテムです。
体育館などの避難所の床は、想像以上に硬く、地面からの冷気も直接伝わってきます。薄い毛布だけでは、底冷えで何度も目が覚め、十分に睡眠を取れません。睡眠不足は体力を著しく消耗させ、免疫力を低下させるため、質の高い睡眠の確保が課題です。
体に巻くだけで体温を逃さないアルミブランケットや、床の硬さ・冷たさを遮断するエアーマットがあれば、睡眠の質を高められます。
大人用紙おむつ・尿とりパッド
介護を必要とする方にとって、大人用紙おむつや尿とりパッドは食料と同じレベルの生命線です。避難所では支援物資が届いても、サイズが合わなかったり、必要な種類が手に入らなかったりすることが多くなっています。
替えがないという不安は、ご本人と介護者の双方にとって大きな負担となり、尊厳にも関わります。物資が届かないことに備えて、必ず普段使い慣れているものを多めに備蓄しておきましょう。
使い捨て手袋・マスク
高齢者は免疫力が低下しがちであり、人が密集する避難所では感染症のリスクが高くなっています。インフルエンザやノロウイルスといった感染症は、体力が落ちている災害時には命を落とすことにつながりかねません。
また、介護の際の衛生管理や、トイレの後始末、掃除など、こまめに手袋やマスクを使用することで、ご自身と周りの人を感染の危険から守ることにつながります。避難所では手袋やマスクを着用し、感染を予防しましょう。
【あると格段に安心】高齢者ならではの便利グッズ
これらがあると避難生活の質が大きく向上し、二次的な健康被害の予防にもつながります。これから紹介するグッズは必須ではありませんが、できれば用意しておくことがおすすめです。
折りたたみ杖
災害時の避難路は停電で足元を確認できず、地面には何が散乱しているかわかりません。このような不安定な道では、転倒のリスクが急激に高まります。高齢者にとって転倒による骨折は、そのまま寝たきりになる可能性のある重大な事故です。
折りたたみ式の杖が一本でもあれば、3本で体を支えるため、不安定な道でも歩きやすくなります。また前方の安全を確認する「探り棒」としても活躍するため、転倒という最悪の事態を防ぐためのお守りになります。
携帯用クッション・座布団
携帯用クッションや座布団は、単なる快適グッズではなく、痛みを和らげ、床ずれを防ぐための重要な健康維持アイテムです。
避難所の硬く冷たい床に長時間座り続けると、想像以上に体力を消耗してしまいます。お尻や腰の痛みが続けば、睡眠の質が下がり、ストレスが増大します。さらに、血行が悪化して「床ずれ(褥瘡)」ができてしまうことも。
床ずれは一度できると治りにくく、感染症の原因にもなりかねません。携帯用クッションや座布団を用意し、必要以上の体力の消耗や床ずれを防止しましょう。
入れ歯洗浄剤・専用ケース
入れ歯が不衛生なままでは、口内炎や歯周病を引き起こすだけでなく、繁殖した細菌が唾液と共に気管に入る「誤嚥性肺炎」のリスクを著しく高めます。また、入れ歯が合わなくなると、硬いものが食べられず、栄養が偏り、体力が一気に低下してしまうでしょう。
入れ歯のケアは、栄養摂取と感染症予防の両面から、命を守るために欠かせない習慣です。
緊急連絡先カード・ヘルプカード
緊急連絡先カードやヘルプカードは、救護所の医師や救助隊員、避難所のスタッフが、迅速で適切な支援を行うための情報源です。
災害時の強いストレスや疲労で、意識があっても混乱して、自分の持病や服用中の薬、家族の連絡先などを正確に伝えられないことがあります。緊急連絡先カードやヘルプカードがあれば、意識がない時はもちろん、冷静に話せない状況でも、あなたに代わって医療情報や連絡先を正確に伝えてくれます。
高齢者向け防災グッズ選びのポイント

防災グッズを数多く紹介しましたが、やみくもに揃えるだけでは不十分です。高齢者の方が「いざという時に本当に使える」ためには、次の4つのポイントを意識して選ぶことが大切です。
- 軽さと持ち運びやすさを最優先する
- 食事は「栄養」よりも「食べ慣れた味・やわらかさ」で選ぶ
- 操作が簡単で、説明書がなくても使えるものを選ぶ
- 持病や身体状況に合わせた「自分専用セット」を作る
軽さと持ち運びやすさを最優先する
防災リュックの重さは、体重の10%以内が目安です。体重50kgの方なら5kgまでが無理のない範囲といえます。背負ってみて「重い」と感じるようなら、緊急時に助ける道具ではなく、むしろ避難を妨げる荷物になってしまうでしょう。
やみくもに荷物を詰めるのではなく、中身を必要なものに絞り、ためらわずに軽量化しましょう。
食事は「栄養」よりも「食べ慣れた味・やわらかさ」で選ぶ
強いストレスのかかる災害時は、食欲がなくなったり、食べ慣れないものが喉を通らなかったりすることがよくあります。栄養バランスも大切ですが、それ以上に「これなら食べられる」という安心感が心と体の支えになります。普段から好きな甘いものや、口当たりの良いもの、柔らかい食感の食品を用意しておくと安心です。
操作が簡単で、説明書がなくても使えるものを選ぶ
非常時に、説明書をゆっくり読む余裕はありません。操作が簡単で、説明書がなくても使えるものを選びましょう。
ラジオやライトなどの機械類は、ボタンが大きく、操作が直感的で簡単なものが最適です。購入したら一度箱から出して、操作方法を確認しましょう。
持病や身体状況に合わせた「自分専用セット」を作る
市販の防災セットは、あくまで基本的な薬のみが揃っています。そこに、持病や健康状況に合わせて「これがないと命に関わる」というアイテムを必ず追加してください。予備のメガネや補聴器の電池、血圧計、常用薬や塗り薬などを加えて、自分専用の防災セットを完成させましょう。
防災グッズと合わせて準備すべき3つのこと

どれほど多くの防災グッズを揃えても、それだけでは十分ではありません。モノの備えを最大限に活かすためには、日頃からの行動面の備えが欠かせません。
ここでは、命を守るために大切な3つのポイントをご紹介します。
- 助けを求められる関係を築いておく
- 避難計画を立て、家族や支援者と共有する
- 防災グッズの「管理と実践訓練」を習慣にする
1. 助けを求められる関係を築いておく
災害時に一番頼りになるのは、遠くの親戚よりもご近所さんかもしれません。普段からご近所さんと挨拶を交わし、「いざという時はお願いします」と声をかけられる関係を作っておきましょう。地域の防災訓練に参加して顔見知りを増やしたり、民生委員や地域包括支援センターに相談したりすることも心強い備えとなります。
2. 避難計画を立て、家族や支援者と共有する
緊急時の混乱をできるだけ防ぐために、「どこへ」「どの道を通って」避難するのか、事前に家族や支援者と話し合っておくのも大切です。自治体が発行するハザードマップで自宅周辺の危険な場所を確認し、安全な避難場所までの経路を実際に歩いてみましょう。
離れて暮らす家族とは、災害用伝言ダイヤル171など、災害時の安否確認の方法を決めておくと安心です。
3. 防災グッズの「管理と実践訓練」を習慣にする
防災グッズは、一度用意したら終わりではありません。年に1〜2回は中身を点検し、食品や水の賞味期限、薬の使用期限、電池切れなどを確認する習慣をつけましょう。
点検の際には、リュックを背負って歩いてみたり、ラジオをつけて動作を確認してみたりすることが大切です。そうすることで、非常時にも落ち着いて行動できます。
高齢者に配慮した防災グッズに関するよくある質問

高齢者に配慮した防災グッズに関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。
Q.高齢者が備えるべき防災グッズには何がある?
まずは、水、食料、携帯ラジオ、簡易トイレ、常備薬、お薬手帳のコピーといった、命に直結する「一次持ち出し品」を優先して揃えましょう。その上で、ご自身の健康や持病に合わせて必要なものを追加していくことが大切です。
Q.100円ショップで揃えられる防災グッズはありますか?
はい、あります。特に、軍手、ホイッスル、ウェットティッシュ、アルミブランケット、小分けの救急用品などは、100円ショップで販売されているものでも十分に役立ちます。まずはこうした手軽なものから準備を始め、少しずつ本格的な防災グッズを買い足していくのもおすすめです。
まとめ

今回は、高齢者に配慮した防災グッズと、その準備のポイントについて解説しました。最後に、重要なことをおさらいします。
| モノの備え | 「軽量」「簡単操作」「食べ慣れた味」「自分専用」という4つの視点を意識して選ぶことが重要です。体力や健康状態に合わないものを無理に揃えても、いざという時に使えなければ意味がありません。負担を減らしながら確実に役立つグッズを厳選することが、高齢者の命と健康を守ります。 |
| コトの備え | 日頃から地域との関係を築き、家族や支援者と避難計画を共有し、定期的な点検と訓練を行うことが不可欠です。行動面での準備を積み重ねておけば、災害時にも落ち着いて判断し、スムーズに避難できる可能性が高まります。 |
災害はいつどこで起こるかわかりません。完璧を目指して後回しにするのではなく、「まずはお薬手帳をコピーする」「玄関にホイッスルを置く」など、今日からできることから始めてみることが大切です。ぜひ本記事の内容を参考に、少しずつ防災グッズを揃えていってください。

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!



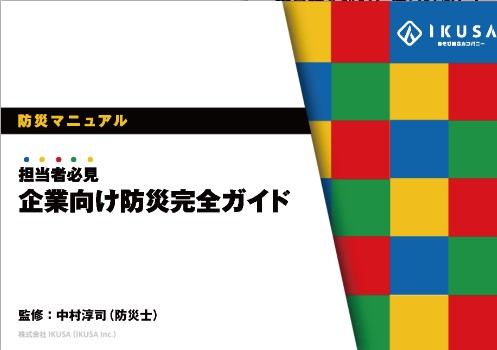





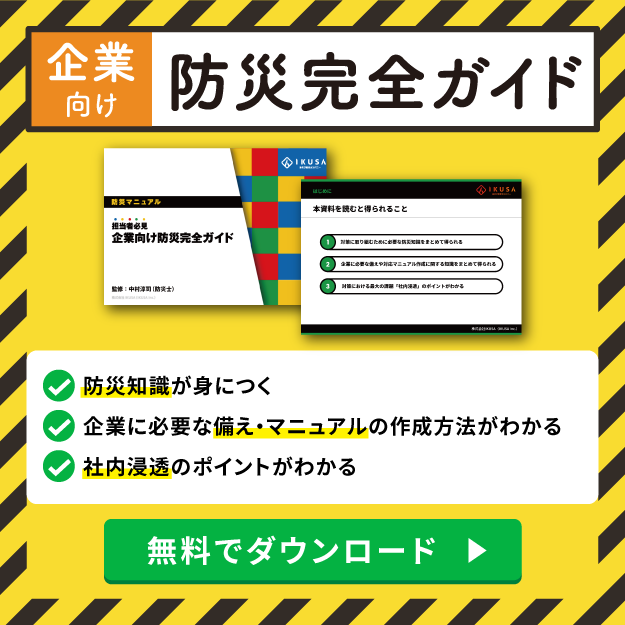







 粕谷麻衣
粕谷麻衣




